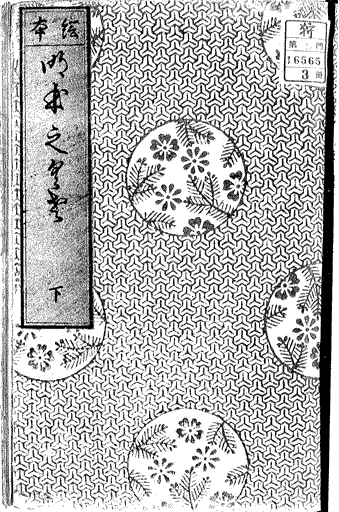 |
(1) 絵本 明ほのくさ 下 |
2021/10/28 改訂 目次へ 表紙へ |
原データ 東北大学付属図書館狩野文庫画像データベース |
明ぼの草上巻へ 明ぼの草中巻へ |
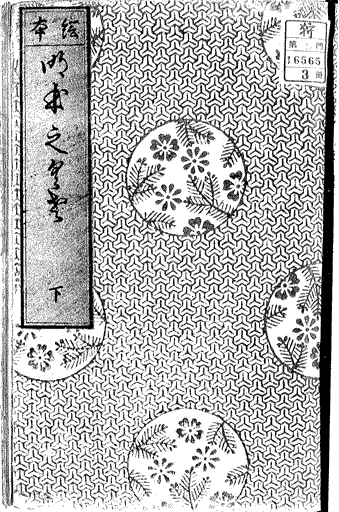 |
(1) 絵本 明ほのくさ 下 |
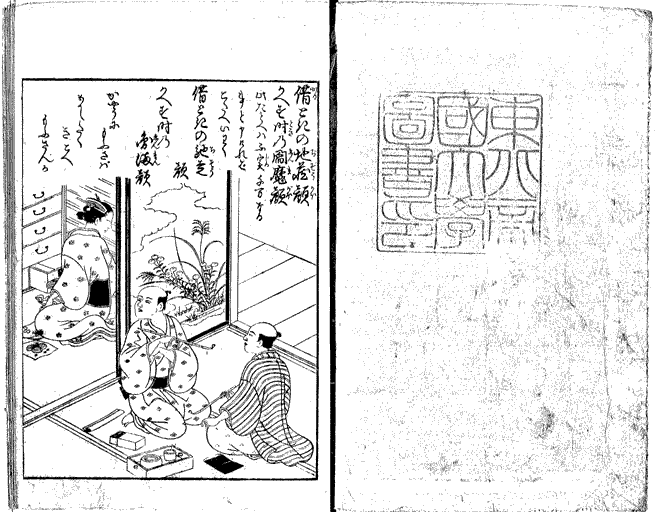 |
(2) 借ときの地蔵顔 かへす時の閻魔顔 此たとへハ不実千万なる 事と申ければ こたへていわく 借ときの馳走顔 かへす時の円満顔 かやうに もふさバ めてたく きこへ もふさんか |
| ○借ときの地蔵顔返す時の閻魔顔 ○用ある時の地蔵顔、用なき時の閻魔顔 他人から金銭などを借りる時はにこにこした 人が、それを返済するときは渋い顔をするということ。 |
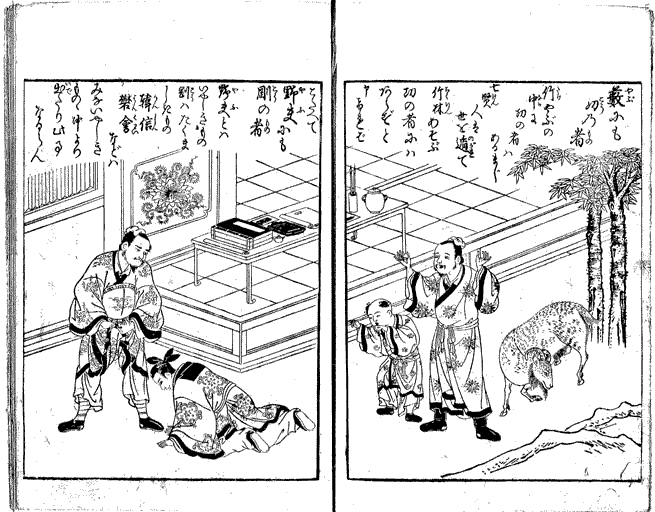 |
(3) 薮にも 竹やぶの 中に功の者ハあるまじ 七賢人は 世を遁(のがれ)て 竹林あそぶ 功の者にハ あらずと 申ければ こたへて 野夫とハ いやしきもの 剛ハたくま しきもの 韓信 みな いやしき ものゝ中より |
| *韓信 漢初の武将。蕭何(しようか)・張良と共に 漢の三傑。江蘇淮陰(わいいん)の人。 高祖に従い、蕭何の知遇を得て大将軍に進み、趙・ 魏・燕・斉を滅ぼし、項羽を孤立させて天下を定め、 楚王に封、後に淮陰侯におとされた。謀叛の嫌疑で 誅殺。青年時代、辱しめられ股をくぐらせられたが、 よく忍耐したことは「韓信の股くぐり」として有名。 (?~前196) *樊會(はん‐かい)漢初の武将。江蘇沛県の人。 高祖劉邦に仕えて戦功を立て、鴻門の会には劉邦の 危急を救い、その即位後に舞陽侯に封。諡(おくりな) は武侯。(―~前189) |
○藪に剛の者 つまらない者の中にも立派な人物 がいる。 また、藪医者の中にも功者がいる。 *七賢 (2)竹林の七賢 晋シン代、世俗をさけて 竹林で音楽と酒とを楽しみ、清談にふけった七人 の隠者。 阮籍ゲンセキ・〔ケイ〕康ケイコウ・山濤サントウ・向秀ショウシュウ・ 劉伶リュウレイ・王戎オウジュウ・阮咸ゲンカンのこと。 絵双紙屋 絵本譬喩節 上巻 薮に剛のもの |
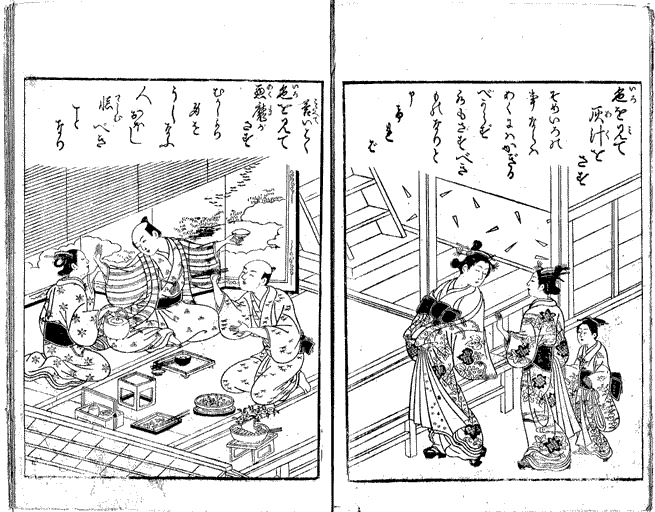 |
(4) 色を見て そめいろの 事ならハ あくにハかぎる べからず 水もさすべき ものなりと 申ければ 色を見て悪魔がさす むかしより 身を うしなふ 人おほし 慎べき ことなり |
| *色(いろ) 恋人。遊女。 ○色は思案の外(ほか) 男女の恋は常識では判断 できず、とかく分別をこえやすい。 ○色を鬻(ひさ)ぐ売春する。色を売る。 ○色を作る 化粧をする。しなを作る。 ○大蛇を見るとも女を見るな 女は人を惑わして 修道の妨げとなるから、大蛇より恐ろしいもの であるとの戒め。 |
○色を見て灰汁をさす 染色で灰汁を加えるとき には色の具合いを見て加減をするところから、時 と場合に応じて適当な手段を取ること。 無闇に事を行なわないという戒め。 ○水をさす (1)水を加えてうすめる。 (2)うまくいっているのに邪魔をして不調にする。 「二人の間に―」 |
*挿絵右頁は太夫(花魁)二人と振袖 新造。左頁は新吉原待合茶屋で飲食 する客と太鼓持ち、茶屋の女。 |
|||
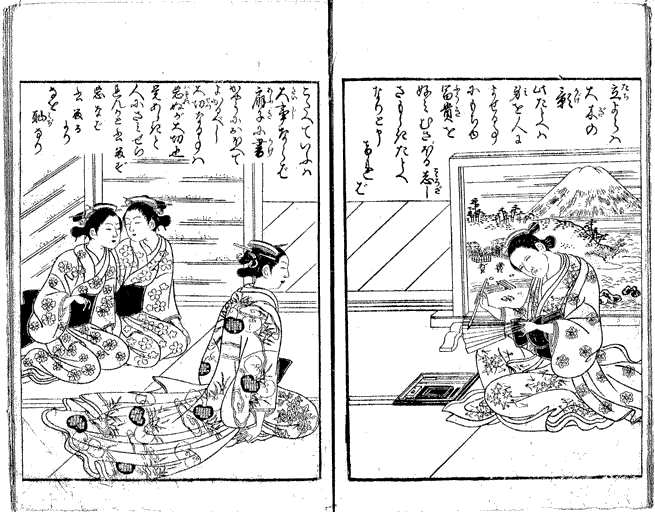 |
(5) 1立よらハ大 此たとへハ 身を人に よせる事にもちゆ 好ミ、むさぼる さもしきたとへ なりと申 ければ こたへていふハ 大事ならば かやうにおほへて よかるべし 大切なる事ハ 忘ぬが大切也 覚あしきと 人に2さミせら れんかと書留ず 忘なば 書留るより なを(猶) 恥なり |
| 2さみす(褊す) みさげる。卑しめる。 軽んじる。 *束帯着用の際は右手に笏(しゃく)を持つが、笏 はもとは裏に紙片を貼り、備忘のため儀式次第な どを書き記したことから笏を扇に替えて、大切な ことは扇に書き留めておくべき。 礼装に扇は必携品なのでいざというときに役立つ。 |
1○立ち寄らば大木の陰 ○寄らば大樹の蔭 頼る相手を選ぶならば、力 のある者がよい。 |
*挿絵は大名家の奥向きに仕えた 奥女中達か。 |
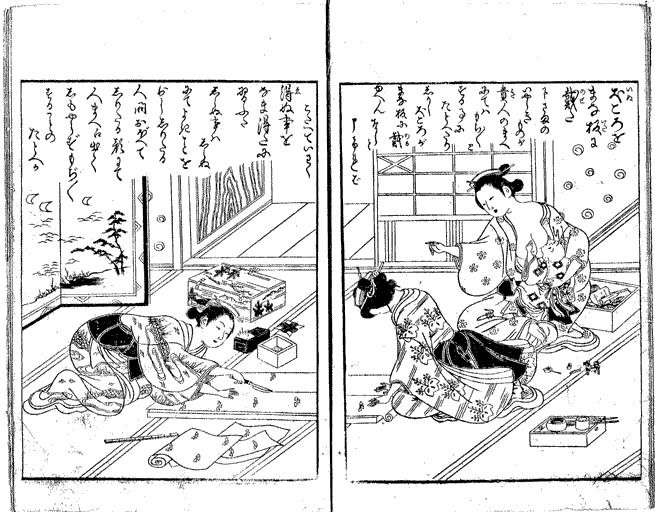 |
(6) 1犬ころをまな板に 下さまの いやしきものが 貴人のまへ にてハもちもぢと する事にたとへたり しかし犬ころが まな板に 申ければ こたへていわく しらぬ事ハしらぬ にてよきことを 少ししりたる 人間おぼへて しりたる顔にて 人まへ江出て ゑもやらず、もぢもぢ することの たとへか |
| ○知らずば人に問え ○聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥 ○問うは一旦の恥 問わぬは末代の恥 |
1○犬ころまな板に乗せた ○犬の子を屋根に上げたよう どうしようもなくて手も足も出ないことの たとえ。 またうろうろして落ち着かない様子にいう。 |
*挿絵はへらで布にしるしをつけている 裁縫中の若い娘。授乳中の内儀が指図 している。 まわりに物さしと布、針箱など裁縫具 がみえる。 |
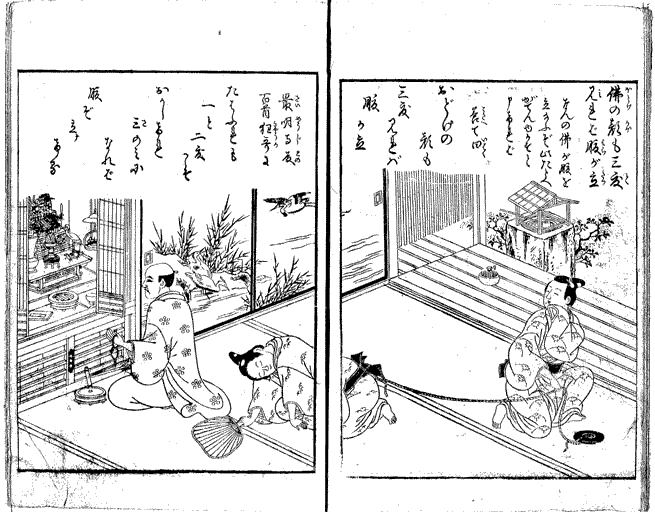 |
(7) 佛の顔も三度 見れば腹が なんの佛が腹を 立給ふぞ 此たとへ がてんゆかすと 申ければ 答て おどけの顔も 三度みれバ腹か立 百首狂歌に たはふれも 一と二度こそ おかしけれ 腹ぞ立チける |
|
*最明寺殿 北条時頼 鎌倉幕府の執権。時氏 |
○仏の顔も三度 いかに温和な人、慈悲ぶか い人でも、たびたび無法を加えられれば、 しまいには怒り出す。 絵双紙屋 顔も三度 おどけ(戯け)おどけること。 *三のみ さのみ 三の意と、そうばかりの意。 |
*挿絵は仏壇の不動明王にお経を唱 える主人とそばで団扇をもったまま 居眠りをする少年とその少年に悪戯 する少年。廊下の前に屋根付き蹲い・ 蹲踞(つくばい)手水鉢がある。 |
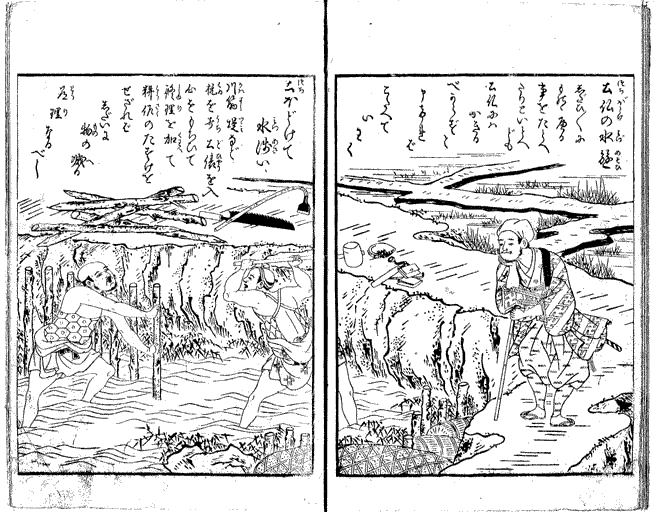 |
(8) しだひしだひに ものゝへる 事をたとへ たりといとへども 土仏にハかきる べからずと 申ければ こたへていわく 心をもちひて 耕作のたすけを せざれば しだいに 物の減る 道理なるべし |
| ○土人形の水遊び ○雪仏の湯好み ○雪仏の湯嬲(なぶ)り ○雪仏の水遊び |
○土仏の水遊び[=水なぶり・水狂い] 土が水中 で溶けて崩れてしまうところから、危険が身に迫る ことを知らないで、自分で自分の身を破滅に導くこ と。身の程知らずなことをして、自分を破滅させる こと。 |
*挿絵は護岸工事のため人足が杭打ち をしている。岸には手斧、大鋸、人足 の煙草入れが置いてある。川岸に工事 監督。 |
|
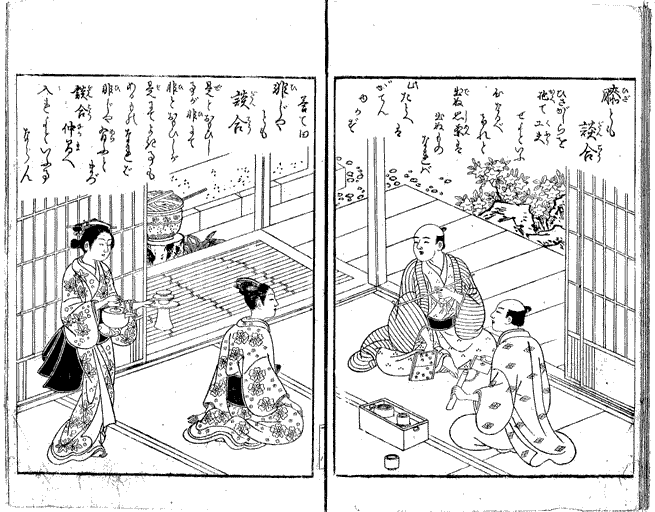 |
(9) ひさがしらを 心なるべけれと 出ぬ思案は出ぬものなれバ 此たとへは がてん ゆかず 答て曰 あるものなれば 談合 仲間へ 入れよといふ事 ならん |
| 良寛漢詩 是非は始より己(おのれ)に在り 道は固(もと)より斯くの若くならず 竿を以て海底を極めんとすれば 祗(た)だ疲れを覚ゆるのみ |
○膝とも談合 (窮した場合には自分の膝でも相談 相手にするという意) 誰とでも相談すれば、それ だけの利益はある。〈毛吹草二〉 *今是昨非 コンゼサクヒ 過去のあやまちにはじめて気 づくこと。 ▽きょうは是(よい)であり、きのうは非(悪い)で あるの意。 〔陶潜〕 帰去来辞 ききょらいのじ |
*挿絵右頁二人の男(町人)はそれぞ れ煙管(きせる)と 腰差煙草入を手 にしている。側に煙草盆。庭先に手水 鉢。 |
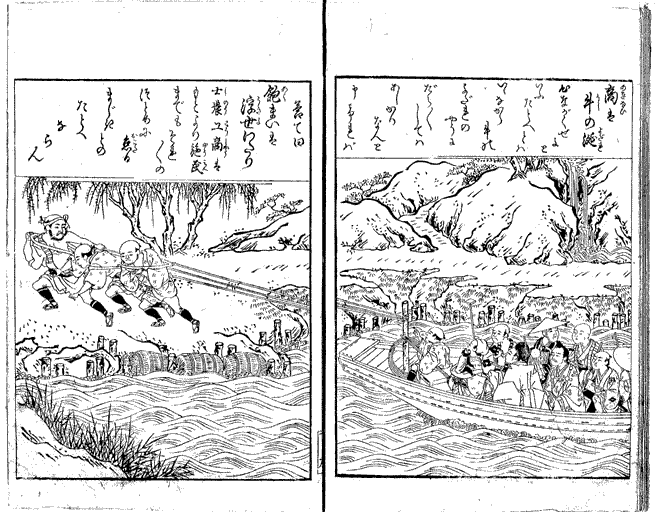 |
(10) 心ながくせよと いふたとへとハ いゝなから牛の よだれのやうに だらだらしてハ あしかりなんと 申けれバ 答て曰 士農工商は もとより までもそれそれの つとめに まじきとの たとへ ならん |
| *飽くまい 飽くまじ 憂き世(浮世)渡りのなりわい(生業)は決し て飽きてはいけない。 |
○商いは牛の涎(よだれ) 商売をするのなら、 牛の涎が細く長く垂れるように気長に辛抱しな さいという教訓。儲けを急ぎ過ぎるなというこ と。 |
*挿絵は三人の渡し守が舟を着岸させて いる。舟に貴賤別なく大勢の乗客。 |
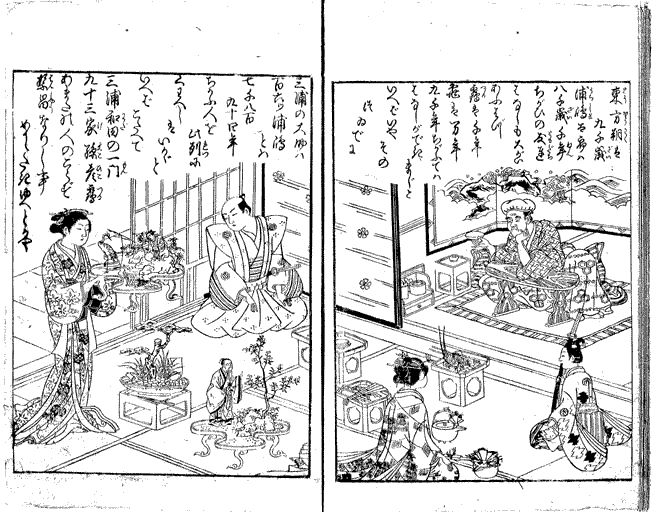 |
(11) 浦島太郎ハ八千歳、千年 ちがひの友達 はなしも大がい あふはづ 鶴は千年 亀は万年 九千年ちがふてハ はなしができまじと いへば、いやその つゐでに 三浦の大助ハ 百六ッ、浦嶋とハ 七千八百九十四年 ちかふ人を 此 くわへしは いかゞと いへば こたへて 三浦和田の一門 九十三家、 あまたの人のこらず 繁昌なりし事 めてたきゆへとかや |
| *三浦大助(みうらのおおすけ) 平安末期 の武将・三浦義明(1092-1180)。相模の有 力豪族・三浦氏の総帥で、治承2(1178)年、 源頼朝の挙兵に応じたが、石橋山の合戦で 頼朝が敗北後、居城の衣笠城に篭城。 一族の主力を安房に落とし、自らは敵勢を 引き受け、城を枕に壮絶な討死を遂げた。 古来まれな長寿者として、誇張して伝承さ れ、「三浦大助」として登場する。 歌舞伎「石切梶原」では106歳とされている が実際には88歳で没。 |
*東方朔(とうほうさく・とうぼうさく) 前漢、厭次エンジ(山東省北部)の人。漢の武帝 に仕え、とんちがあり、巧みに武帝のあやまち を戒めた。また東方朔は西王母という仙人の仙 桃を盗んで食べ、仙術を得て長寿を得たという。 古来めでたい主題としてしばしば絵に描かれる。 *浦島太郎 雄略紀・丹後風土記・万葉集・浦島 子伝などに見える伝説的人物で漁夫。亀に伴われ て竜宮で三年の月日を栄華の中に暮し、別れに臨 んで乙姫(亀姫)から玉手箱をもらい、帰郷の後、 戒を破って開くと、立ち上る白煙とともに老翁に なったという。 *歌は大晦日や節分の夜などに唱え言をして米銭を 乞うてまわった厄払い文句の一節。 |
*挿絵は新年の蓬莱飾り。関西で新年の 祝儀の飾り物の一。三方(さんぼう)の 盤の上に白米を盛り、熨斗鮑(のしあわ び)・搗(か)ち栗・昆布・野老(ところ) ・馬尾藻(ほんだわら)・橙(だいだい) ・海老(えび)などを飾ったもの。 江戸では食い積みと呼んだ。 松竹梅・鶴亀・翁(おきな)と嫗(おうな) などを取り合わせて飾ることもある。 |
「古典落語ネタ帳」の中の『厄払い』にこの文章とよく似た「口上」が掲載されています。
出典:古典落語集2 文楽 (ちくま文庫) 厄払い とみくら まさや氏HP |
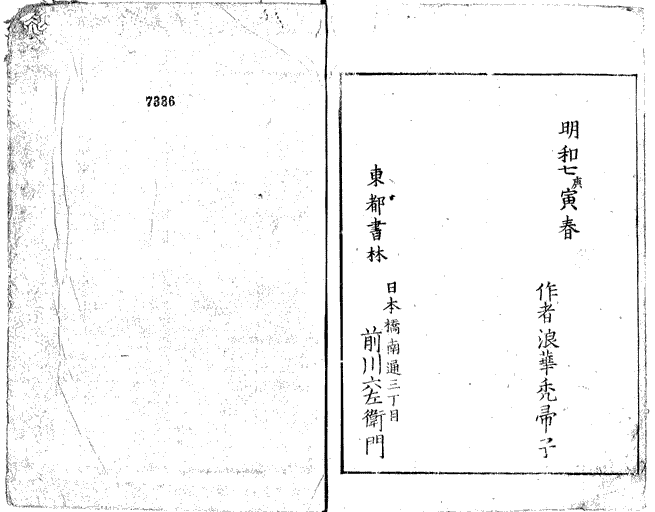 |
(12) 明和七庚寅春 作者 東都書林 日本橋南通三丁目 前川六左衛門 *明和七庚寅 (1770年) |