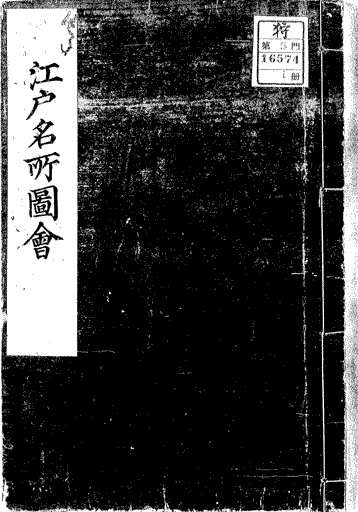 |
(1) 江戸名所図会 |
表紙へ戻る 目次へ戻る 2020/3/3改訂 |
江戸名所図会 (えど めいしょずえ) 一冊 十偏舍一九 画 (十返舎一九) 文化十年序 (1813年) 原データ 東北大学 狩野文庫画像データベース |
| 解説 江戸の名所、上野・日暮里・王子・神田・吉原・隅田川・亀戸・日本橋等々の 景色風俗にちなんだ狂歌五十一首(狂歌師五十名の狂歌)に十返舎一九の序文と 画が添えられている。墨摺絵本。 十返舎一九(一世)(1765~1831)は江戸後期の戯作者。本名、重田 近松余七と号して浄瑠璃作者となり、寛政五年(1793年)江戸に出て蔦屋重三郎 に寄宿して戯作に従事し、絵師として、あるいは絵師と戯作家を兼業で自画作の 作品を多数書き描いた。 その後、戯作家として黄表紙、狂歌絵本、往来物、洒落本、合巻、咄本、滑稽本な ど広い分野に大活躍し、生涯にわたって約600冊もの著作を書き続けた。 代表作は「東海道中膝栗毛」「江之島土産」など。 翻刻と注釈に関しては古文書研究家羽生榮氏と福岡県在住の松尾守也氏にご協力 を頂きました。厚く御礼申上げます。 |
|---|
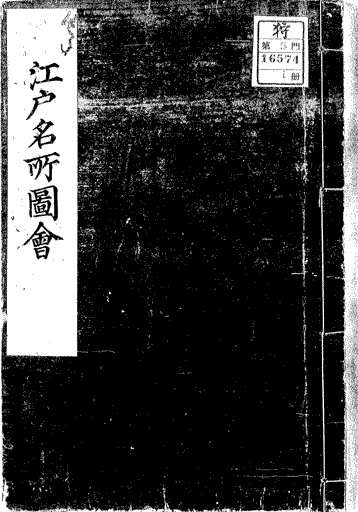 |
(1) 江戸名所図会 |
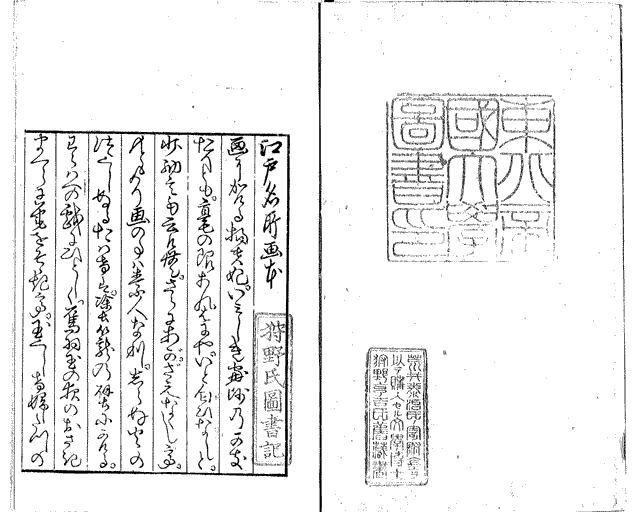 |
(2) 江戸名所画本
1画にかける楊貴妃。 いミしき画師のかき たりとも。毫の限あれは にや。いと匂ひなしと。 少納言も云けむ。さらに あが。ざえなくして。 もとより画の事ハ素人 なり。2しらぬ火の つくしぬる たハけは。 3塗籠の壁にかける。 わらハへの戯にひとしく。 4烏羽玉の夜のおさき まくらに筆をそゝきて。 5玉くしけふたつの |
| 1源氏物語の桐壺の巻に「絵にかける楊貴妃 の容貌(かたち)はいみしき絵師といへども、 筆限り有ければ、いとにほひすくなし」 の引用から少納言とは紫式部を指すのだろう か。 2不知火・白縫 「筑紫」にかかる枕詞。 「筑紫」は「尽し」の掛詞。尽くせぬほど のばかもの。 3寝殿造りの母屋(もや)の一部を仕切って、 周囲を厚く壁で塗りこめた閉鎖的な部屋。 寝室。 4うばたまの(烏羽玉の)枕詞。 「ぬばたま(射干玉)の」に同じ。「黒・夜・ 夕・月・暗き・今宵・夢・寝」などにかか る。ここではお先まくら(真っ暗)にかけ た。 5玉櫛笥「くしげ」の美称。「み・ふた・ おほふ・ひらく・あく・奥」にかかる枕詞。 櫛笥櫛などの化粧道具を入れておく箱。 |
(現代語訳)
|
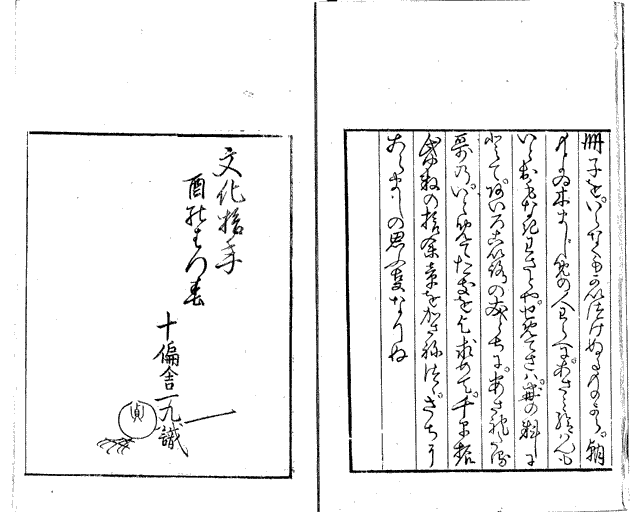 |
(3) 冊子を。いらなくもかいつ けぬるものから。1朝 もよゐきまじめの人わらへ に。2あさミ給ハんも いと3おもなきわさとや。 せめてさハ。画の料に とて。4あいろこいろの友 とちに。5あされたる 歌の。いとめてたきを乞求 めて。6千早振 紙数の拾余章をかさね つゝ。さちに あらましの思ふ事なりぬ。 文化拾年 酉のはつ春 7十偏舎一九識 |
| 1あさもよし(麻裳よし)は(紀伊国からよい 麻を産出したので) 「き(紀・城)」にかかる枕詞。ここでは次の 言葉「きまじめ」の「き」に掛る。人わら へ「ひとわらはれ」に同じ。 2驚きあきれる。 3面無し 人にあわせる顔がない。恥か しい。 4あちこち。 5あざる(狂る・戯る) たわむれる。 ざれる。ふざける 6「神」「うぢ」などにかかる枕詞。 次の「かみ(紙)に掛ける。 7十偏舎一九の名前の横に熊手と菅笠が描 かれている。笠の端に本名の貞一の貞の 字が書かれている。この印は一九著の 他の絵双紙にも見られる。また浅草の東 陽院(東京都中央区勝どき四丁目に移転) の一九の墓碑にもこの印が彫られている。 文化十年(1813年) |
(現代語訳)
|
||
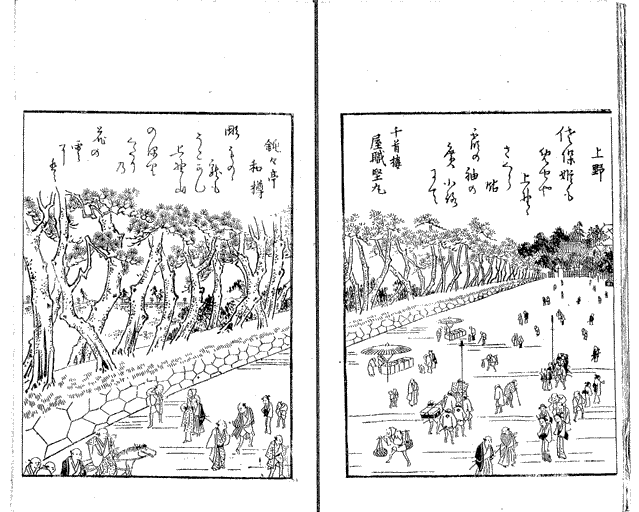 |
(4) 1上野 2佐保姫も めセや上野の さくら飴 霞の袖の 3広小路にて 千首楼 屋職堅丸 4 彫ものゝ 龍もうこかし 上野山 のほりくたりの 花の雲にと |
| 4鈍々亭 和樽(どんどんてい わたる) 別名 祭和樽(まつり わたる) この絵双紙の28頁にも一首掲載されている。 |
1東京都台東区上野。現在、上野公園はもと寛永 寺の境内で、江戸時代桜の名所で賑わった。 寛永寺は天台宗の寺。山号は東叡山。1625年 (寛永2)天海が開山。歴代住持は法親王で、輪 王寺門跡を称した。徳川将軍家の菩提所。 2春をつかさどる女神。佐保山は平城京の東に 当り、方角を四季に配すれば東は春に当るか らいった。 3上野広小路近辺。当時は下谷広小路。明暦の 大火後に設けられた防火地帯。両側に寛永寺 の門前町がひらけて江戸随所の繁華街となっ ていた。 |
東叡山寛永寺公式ページ |
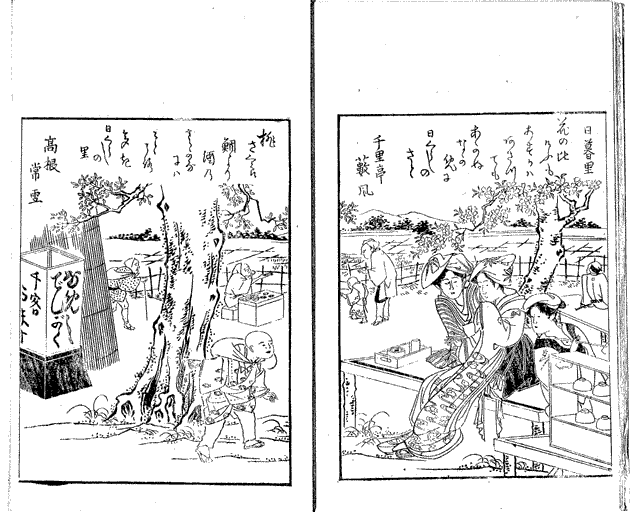 |
(5) 花の 1けふもあすかハ あさつても あか(飽)ぬ なかめ(眺め)に 2日くらしのさと 千里亭 薮風 桃3さくら 鯛より 酒の さかなにハ ミところ 多き 日くらしの里 高根 常霊 なめし(菜飯) でんがく(田楽) 千客□□□ |
| 3さくら 桜と桜鯛とにかかる。桜鯛はサクラの咲く時 期に捕れる真鯛のこと。刺身・焼き魚として 美味。色が華やかで姿が立派なところから、 祝いの場で使われる。 |
1日暮らしの里 日暮里はかつて新堀(にい ほり)という地名だったが、享保のころから 「一日中過ごしても飽きない里」という意味 を重ねて「日暮里(日暮らしの里)」の字が 当てられ、1749年(寛延2年)に正式な地名と なった。東京都日暮里の青運寺(俗称花見寺) から浄光寺(俗称雪見寺)周辺の寺々は道灌 山から続く地域で「此辺寺ノ庭中景至テ見事」 と当時の江戸の地図にも記載されている景勝 地。 2今日もあすもあさってを畳み掛けて、 「明日か」と「飛鳥山」を掛ける。 「飛鳥山」は東京都北区王子にある小丘陵。 古来、桜の名所。 ○けふもまたあかぬ眺めに暮れはてぬ あはれたちうき花の陰かな (正治初度百首 御室 318守覚法親王) |
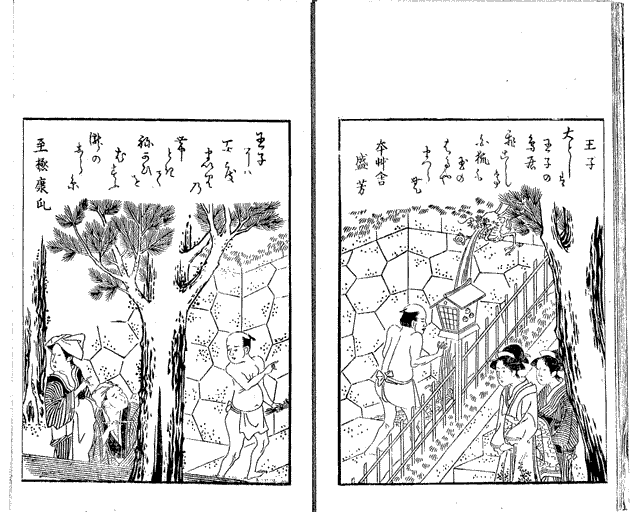 |
(6) 1王子 2大としは 王子の鳥居 飛こして 白狐も玉の はるやまつらむ 本草舎 盛芳 王子にハ 百度まいりの 帯ときて ねかひをむすふ 瀧のしら糸 至極 康瓜 |
| 「帯解き」と「願ひを結ぶ」が対句。 (挿絵)王子稲荷境内の瀧で水垢離(みずごり) をする下帯姿の男二人と床店の夫婦、参拝の 女達。 「絵本江戸土産」(1753年刊)の王子岩屋の挿 絵にも稲荷社境内で瀧を浴びて水垢離する様 子が描かれている。 (絵本江戸土産 絵双紙屋HP中) |
1王子稲荷 東京都北区岸町。関東の稲荷神社 の総本社。大晦日の夜には関東の狐が集まり、 榎の大木(装束稲荷)で衣装を調えてお参り したという伝説をもとに、狐の格好をして装束 稲荷から王子稲荷へと行列する王子狐の行列 が行われ、多くの参拝客でにぎわうという。 2大年 大みそか。大みそかの夜。 |
王子稲荷神社 |
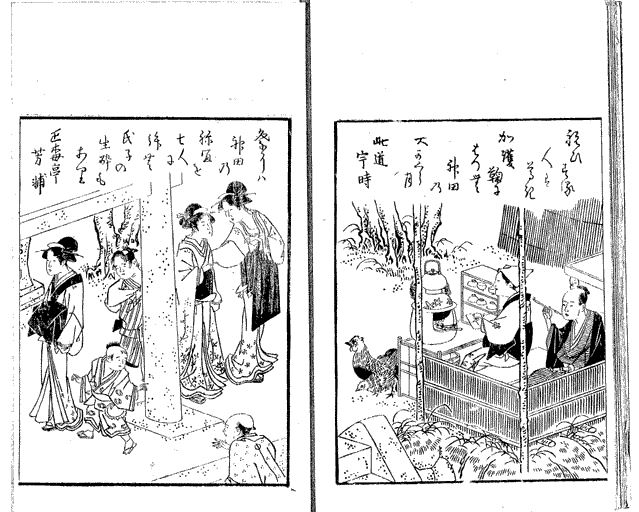 |
(7) 祝ひする 人は尊き 加護鞠に はつむ1神田の 2大かくら月 此道 宇時 3祭にハ 神田の 4七人に 拝む氏子の 生酔もあり 近梅亭 芳輔 |
| 3神田祭 東京の神田明神の祭礼。 5月15日(もと9月15日)。本祭と陰祭とを隔年 に行い、神輿巡幸・山車・踊などでにぎわ う。山王祭と共に天下祭と呼ばれ、江戸二 大祭の一。 4七人 神田の祢宜七人を竹林の七賢人にな ぞらえたのか。 ○古(いにしへ)の七の賢しき人どもも 欲(ほ)りしせしものは酒にしあるらし 万葉集 三・340 宰帥大伴卿讃酒歌 |
1神田神社(神田明神)天平2年(730) 現千代田区大手町に大己貴命を祀った のが始まりで、延慶2年(1309)に平将門の 首塚を相殿に合祀して神田明神と名付けら れたという。元和2年(1616)徳川2代将軍 秀忠が現在地に遷座し社殿を築き、江戸 総鎮守(武州総社)として、また 江戸城表 鬼門の守護神として歴代将軍に崇敬された といわれている。 2太神楽 雑芸の一種。獅子舞のほか品玉・ 皿回しなどの曲芸を演ずるもの。天下祭りの、 神田明神祭礼には太神楽は祭りの先払いの役 を勤め、将軍家の台覧も蒙り、華麗な芸は江戸 の風物詩ともなった。この江戸神楽は10種類の 曲芸が演じられたが、うち4つに「鞠」が使わ れていた。 なお神楽月は 陰暦十一月の異称。 |
神田明神 公式ページ |
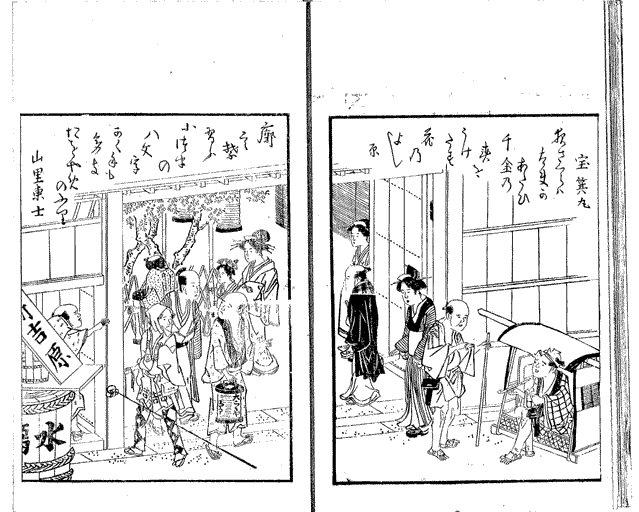 |
(8) 宝 箕丸 夜さくらハ 1大夫か2あたひ 千金の 春をうけたす 花の3よし原 4廓言葉 習ふ5小つま(褄)の 6八文字 かく手も多き たをやめ(手弱女)のふり 山里 東士 (新)吉原 |
| 4廓言葉 遊郭で遊女の使用することば。田舎 詞を使わせぬために定めたものという。 「ありんす」の類。 5○褄をとる 裾の長い着物の竪褄(たてづま) を手で持ち上げて歩く。普通、芸者が左褄を とるのにいう。 6八文字 花魁道中で花魁が行う特殊な歩き 方。花魁道中の際、京都島原や大阪新町で は「内八文字」で、両足の爪先を内側に向 けて「八」の字の形に歩いた。一方江戸吉 原では「外八文字」で、一旦内にむけた爪 先を更に外方に向けて足を運ぶ歩き方を行 っていた。(江戸吉原では明暦頃までは内 八文字であったが、一説によれば明暦の頃、 勝山という遊女が外八文字の歩き方を始め たという。)なお、花魁が履く黒塗りの下 駄は三枚歯下駄なので、重いこともあって、 普通に歩くことが出来ないために独特の歩 き方をした。きちんと八文字で歩けるよう になるには三年かかったともいわれる。 |
1大夫 最上位の遊女。 2○春宵一刻値(あたい)千金[蘇軾、春夜 詩「春宵一刻直千金、花有清香月有陰」] 花は盛りで月はおぼろな春の夜の一刻の情 趣は、千金にもかえがたい価値がある。 3吉原 江戸の遊郭。1617年(元和3年) 市内各地に散在していた遊女屋を日本 橋葺屋町に集めたのに始まる。明暦の大 火に全焼し、千束日本堤下三谷(さんや) (現在の台東区浅草北部)に移し、新吉原 と称した。北里・北州・北郭などとも呼 ばれた。周囲は「おはぐろどぶ」という 堀で囲まれていた。入口は大門口。 |
*挿絵 吉原の大門か。 左頁の右端に、横に禿、後ろ に新造を連れた花魁が描かれ ている。門の縁石を踏んでい る男二人。提灯を提げている のが「露払い」、鉄棒を持っ ているのが鉄棒曳き(かなぼ うひき)であろう。この両名 は花魁道中の先頭を歩く。 |
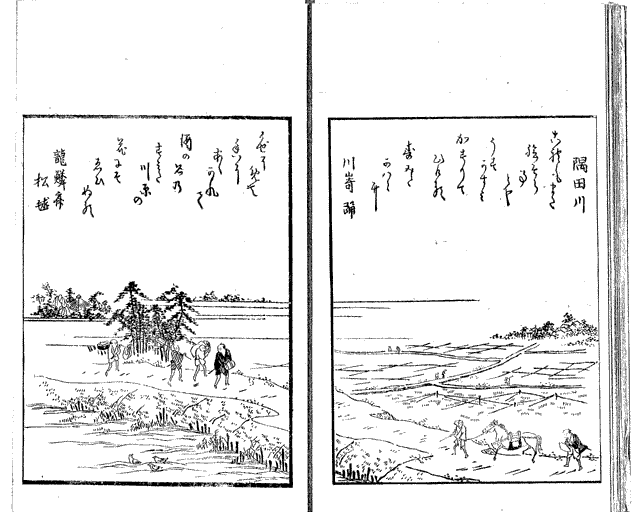 |
(9) 1隅田川 これもまた 絵そら事とヤ うすかすミ(薄霞) かすりてひける すみた 2かハの竹 川崎 踊 色にめて 香に3あくかれて 酒の名の すミた川原の 花にそゑ(酔)ひぬる 龍鱗斎 松毬 |
| 3あくかれ 憧る。居所を出て浮かれ歩く。 清酒(すみざけ)のすみと隅田川のすみ。 花と吉原の花の遊女をかける。 |
1隅田川 (古く墨田川・角田河とも書いた) 東京都市街地東部を流れて東京湾に注ぐ川。 もと荒川の下流。広義には岩淵水門から、通 常は墨田区鐘ヶ淵から河口までをいう。東岸 の堤を隅田堤(墨堤)といい、古来桜の名所。 大川。 2川の竹 川(河)竹。遊女の身の上。 ○卵の四角と女郎の誠 あるはずのない たとえ。 |
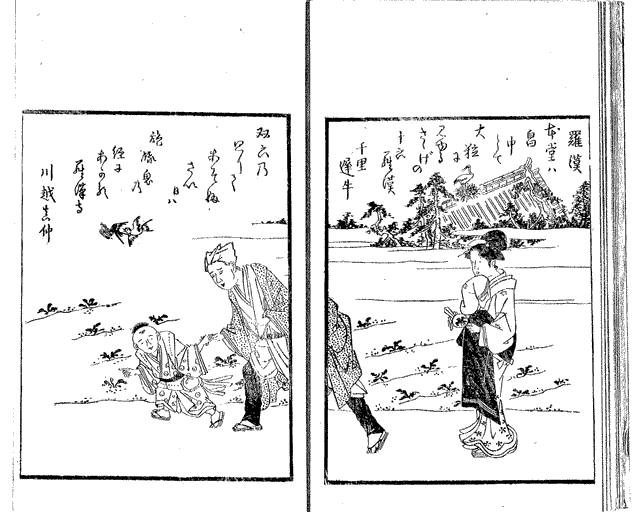 |
(10) 1羅漢 本堂ハ 大粒に 見ゆるさゝげの 2十六羅漢 千里 遅牛 3双六の 廻りてあそふ 4さい日ハ 5施餓鬼の経に あかる羅漢寺 川越 真仲 |
| 3双六(すごろく) (1)盤双六。二人が対座して、二個の采(さい) を木または竹の筒に入れて振り出し、出た目 の数だけ盤に並べた棋子(駒石)を進め、早く 相手の陣に入ったものを勝とする。古くから 賭博として行われ、鎌倉幕府や江戸幕府の禁 令にも度々見られている。(2)絵双六。 紙面に多くの区画を描き、数人で(1)に準じて 勝負する。正月の子供の遊びとなる。 ここでは盤双六のことか。 4斎日(賽日)・祭日・双六の賽(さい・ さいころ)をかける。 賽日 藪入(やぶいり)に閻魔(えんま)に参る 日、すなわち正月一六日と七月一六日。 5施餓鬼 〔仏〕飢餓に苦しんで災いをなす 鬼衆や無縁の亡者の霊に飲食を施す法会。 今日では盂蘭盆会と混同。 |
1 (1695)、江戸本所五ツ目(現、江東区大 島3丁目)に創建された黄檗宗の名刹。 明治41年(1908)、目黒に移転した。 羅漢堂の五百羅漢像は、寺院の創建に尽力 した松雲禅師の作で、現存するのは305体。 2十六羅漢 〔仏〕[法住記] 永くこの世に在住 して正法を護持するという16人の羅漢。 「十六羅漢」と「 ささげ)・「大角豆」(ささげ)と「捧げ」 を利かす。 |
五百羅漢寺 ウィキペディア 双六コレクション 東京学芸大学 |
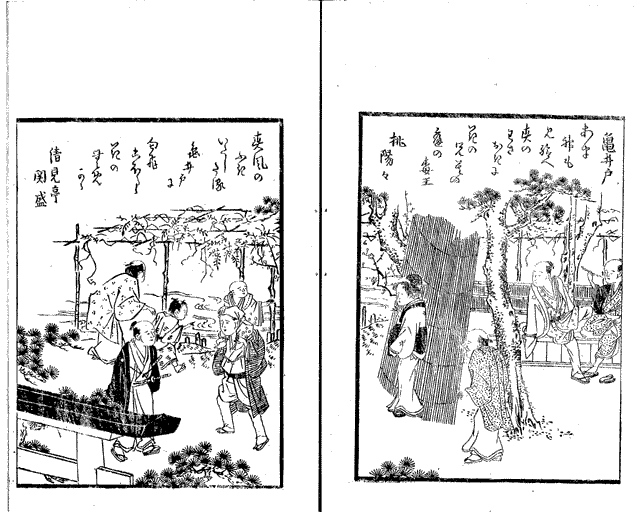 |
(11) 1亀井戸 あま神も 見給へ春の 2わさおきに 3花の兄貴の 庭の梅王 桃 陽々 春風の ふきいたしたる 4亀井戸に 匂ひこほるゝ 花のむめかゝ(梅が香) 偆見亭 関盛 |
| 4亀戸の梅屋敷 「梅屋舗」は亀戸天満宮の北 東の裏手、亀戸3丁目の一画にあった梅園で ある。百姓喜右衛門の宅地内にあり、清香庵 といった。ここにあった臥龍梅で特に有名。 は有名 ○東風(こち)吹かばにほひおこせよ梅の花 あるしなしとて春をわするな (拾遺集 巻16 雑春 1006 道真) |
1亀戸天神 東京都亀戸にある亀戸天神社 |
亀戸天神社 公式ページ 名所江戸百景・亀戸梅屋舗 |
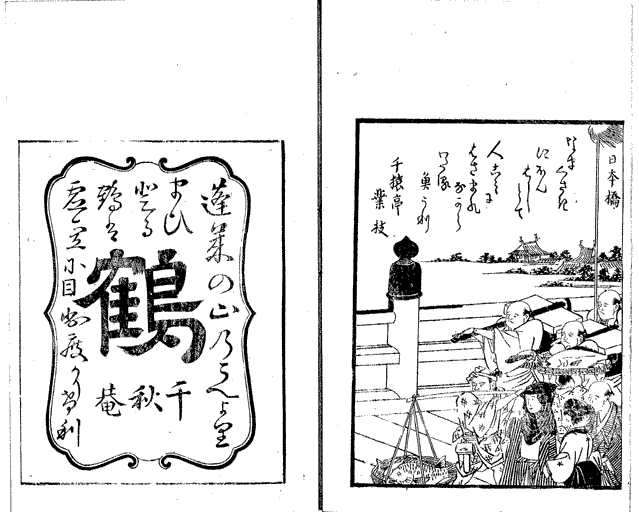 |
(12) 1日本橋 なまくさき にほんはしとて 人こミに はさまれなから わたる魚うり 千猿亭 業技 鶴 蓬莱の山のうへより まひ 登る 鶴は 虚空に目出度かりけり 2千秋庵 |
| (挿絵)日本橋の賑わい。供揃えの大名行列 (挟箱を背負う奴二人に毛槍を持つ中間が続く) のすぐ横を天秤棒を担ぐ魚屋、大きな魚籠を 掲げて反対側へ往く男、さまざまな町人達が 通る。 *この挿絵では大名行列の横を歩く町人達が平伏 していないことに注目。時代劇等では、大名行列 が往来を通り過ぎるときには必ず先導の旗持ちの 「下に~、下に~」との声にあわせ百姓、商人な どは脇により平伏しているシーンが登場するが、 実際にはこの掛け声を使えるのは徳川御三家の尾 張・紀州藩(水戸藩は例外で江戸常勤であるため 参勤交代はなかった)だけで、ほかの大名家は 「よけろ~、よけろ~」という掛け声を用い、一 般民衆は脇に避けて道を譲るだけでよかった。 また、歌川広重の「東海道五十三次之内 日本 橋朝之景」にも大名行列の脇で天秤棒を担いだ まま平伏せずに行列一行の通過を待っている情 景が描かれている。 |
1生臭き日本橋 日本橋は東京都中央区にあ る橋。隅田川と外濠とを結ぶ日本橋川に架 かり、橋の中央に全国への道路元標がある。 1603年(慶長八)創設。周辺には金座をはじ め、江戸城下の鮮魚を一手に扱う魚河岸や 大店が軒を並べ日本橋は大変に賑わった。 日本橋北詰東側には日本橋魚河岸記念碑が 残されている。 2この絵双紙終わりの(29)に千穐庵・三 陀羅法師という号名で一首掲載されている。 |
(大名行列 ウィキペディア) 「東海道五十三次之内 日本橋朝之景 |
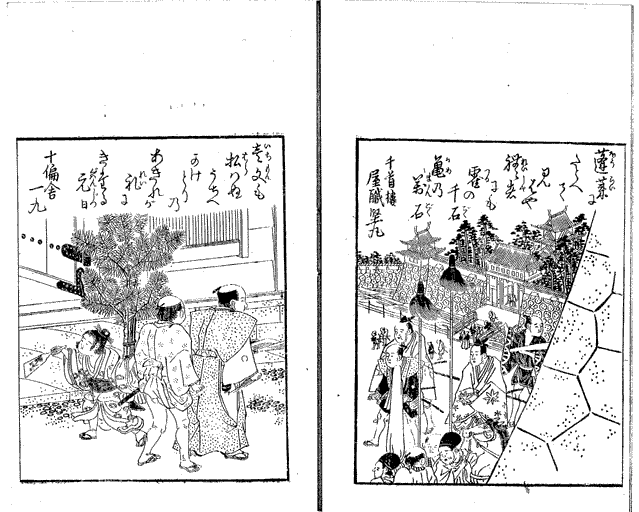 |
(13) 1 たとへて見はや 2 3鶴の千 亀の 千首楼 屋職堅丸 壱文も 払ハぬうちへ 4かけと(掛取)りの あき(呆)れが礼に きたる元日 十偏舎 一九 |
| 4掛取り 掛売りの代金を取り立てること。 また、その人。近世には、歳末だけ、ある いは歳末と盆との二度であった。 ○呆れが礼に来る ひどく呆れかえるのに いう。 |
1蓬莱 蓬莱にかたどって作った台上に、松 竹梅・鶴亀・尉姥(じよううば)などを配し、 祝儀などの飾り物に用いるもの。 2礼者 年賀にまわり歩く人。 3○鶴は千年亀は万年 (鶴や亀を神秘化した中 国神仙譚から出た語) 寿命が長くめでたいこと にいう。 |
(挿絵)年頭、将軍への拝賀 の礼を終えて下城する大名 一行。後方に大手門と濠。 |
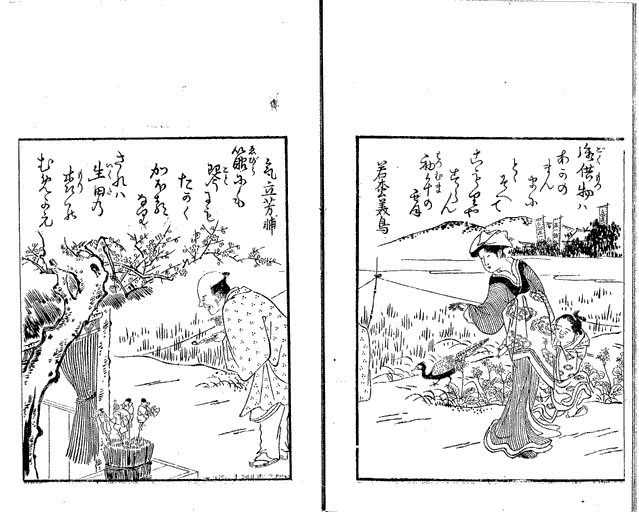 |
(14) 1あかのまんまに とゝ(魚)そへて こもり(子守)やすらん 若松 美鳥 気立 芳輔 琴にもたかく かほるなり されハ4生田の 森のむめかえ(梅か枝) |
|
3箙(えびら) 矢を入れて携帯する容器。 |
1あかのまんま(赤の飯)(1)赤飯。 (2)花・つぼみの形が赤飯に似ているから) イヌタデの別称。あかまんま。 2初午(はつうま) 2月の初の午の日。京都 の伏見稲荷神社の神が降りた日がこの日であ ったといい、全国で稲荷社を祭る。この日を 蚕や牛馬の祭日とする風習もある。 |
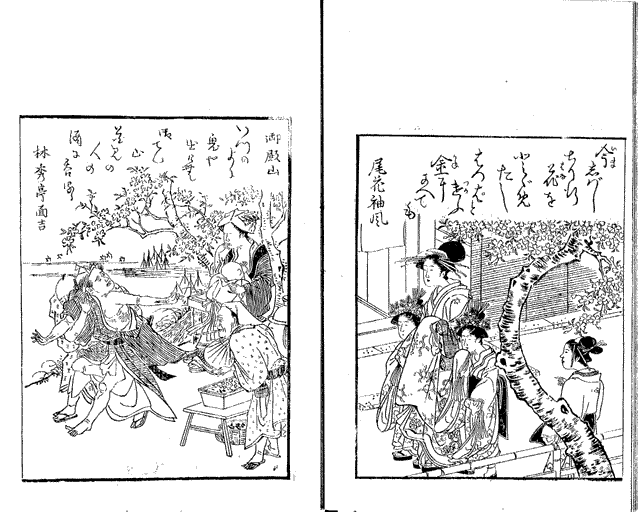 |
(15) 今しバし ちり行花を とゞめたし はつぱ(葉っぱ)と遣ふ 尾花 袖風 1御殿山 いつのよに 鬼や出けむ 御てん山 花見の人の 酒に呑るゝ 林秀亭 面吉 |
| 1御殿山 東京都品川区北品川。元禄15年 (1702)にかけて、この地に将軍家の品川御殿 が設けられ、鷹狩の際の休息所として利用 されていた。桜の名所。 |
○あまつ風雲のかよひち吹きとちよ 乙女の姿しはしととめむ (古今集 巻17 雑上 872 遍昭) (挿絵)吉原の花魁と禿二人。 |
(挿絵)御殿山花見情景。屋台の 亭主と乳飲み子を抱くその妻。 酔っ払いが絡もうとしているの を抱き止める朋輩。亭主の険し い顔。眼下の海は品川沖。沖を 行く帆掛け船と碇泊する船の帆 柱がいくつも見える。船は五大力 船(ごだいりきせん)か。 五大力船は江戸を中心に関東近辺 の海運に用いられた海川両用の廻 船の事。百~三百石程度の大形の 荷物運搬用の帆船。 |
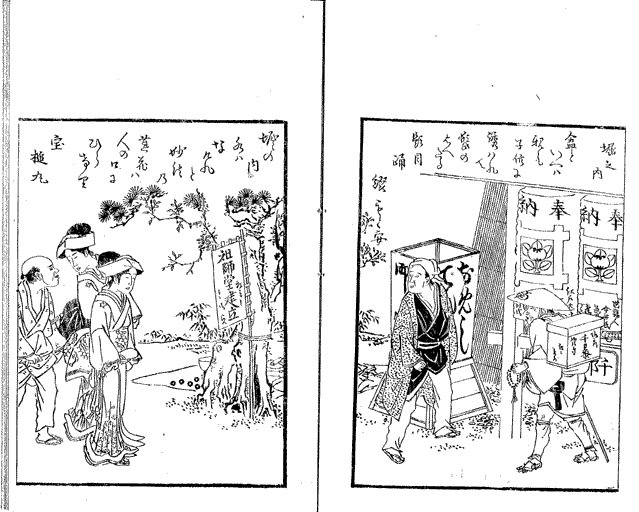 |
(16) 1堀之内 盆といへハ 親も子供に 誘ハれて 髭のはへたる 2題目踊 3錣もと安 奉納 なめし(菜飯) でん(がく) 堀の内 水ハなけれと 妙法の 口にひらけり 宝槌丸 祖師堂建立 |
| 1堀の内 東京都杉並区堀ノ内にある日蓮宗の 日円山妙法寺。この寺に参詣することを 「お祖師様(おそっさま)参り」ともいい、 江戸時代から毎月(特に10月)の13日は参詣で にぎわった。厄除で有名。 2題目踊 陰暦7月16日の夜、太鼓・大鼓・ 拍子木などに合せて法華経の題目を唱えな がら男女合同でする踊り。 3錣(しころ)元安 この絵双紙28頁にも一首 掲載されている。 |
堀之内 妙法寺 公式ページ (挿絵)角隠し姿の女二人。角隠し は浄土真宗門徒の女性が寺参り の時に用いたかぶりもの。 幅およそ12㎝、長さ72㎝の白絹 (裏は紅絹もみ)を前髪にかぶせ、 後で二つ折にして回し、髷(まげ) の後上で留めておくもの。現在 では、婚礼の時に花嫁がかぶる 頭飾り。 |
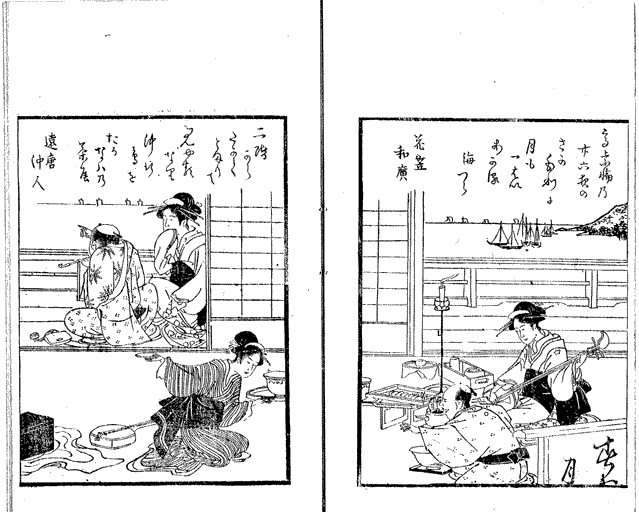 |
(17) 1 2廿六夜の さかもりに 月も一はい あかる海つら 花笠 和廣 二階から たかくとまりて 見ゆるなり 沖行鳥を たかなハの茶屋 3 |
| 3遠唐沖人(えんとう おきんど) この絵双紙28頁にも一首掲載されている。 (挿絵)高輪の茶屋二階座敷。二十六夜待の 場景。酒盛りしながら月の出を待つ客と客を もてなす芸者、仲居もいる。酒料理と二棹の 三味線。二階からは品川沖を行く帆掛け船と 高輪の船溜りが見える。船は五大力船か。 |
1高輪 東京都品川区高輪近辺の茶屋。 2二十六夜待 陰暦の正月と7月との26日 の夜半に月の出るのを待って拝すること。 月光に阿弥陀仏・観音・勢至の三尊が姿を 現われる伝えられ、特に江戸では7月に 高輪(たかなわ)・品川などで盛んに行われ た。月待。 |
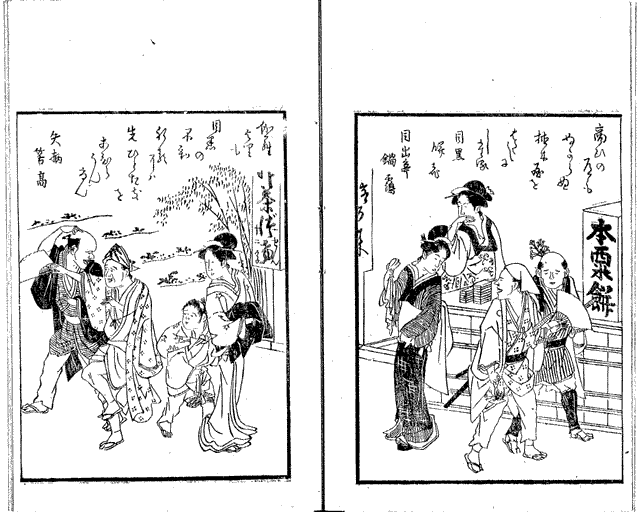 |
(18) 商ひの 道もぬからぬ 植木屋を 1はたしにしたる 目黒2餅花 目出亭 鍋鶴 本粟餅 3目黒の不動 祈るにハ 先ひとたきを 4あひらうんけん (阿毘羅吽欠) 矢柄 筈高 一セん 御茶づけ 十二文 |
| 3目黒不動尊 瀧泉寺(りゅうせんじ)通称、 目黒不動尊。開基、大同3年(808)慈覚大師 円仁。江戸時代には上野寛永寺の末寺となり、 さらに三代将軍家光の帰依を受けて大変栄え た。 4阿毘羅吽欠〔仏〕(梵語) 密教で、胎蔵界大日 如来の真言。地・水・火・風・空の五大を象徴 する。この真言を唱えると一切のことが成就 するという。前に「オン」を、後に「蘇婆訶 (そわか)」をつけて唱えることが多い。 伽羅 香木の種類。沈香(じんこう)の最上の 種類。わが国では最も珍重された。遊郭で金 銭の隠語。 (歌意)伽羅より有り難い目黒お不動様に祈る には、瀧泉寺、霊験あらたかな独鈷の瀧を、 先ずひとたき浴びて、「あびらうんけん」 と祈らん。 |
1はたし 旗師 投機取引をする商人。はた あきない。旗商い・端商い・米相場・銭相場 などで、現物をもたずに思惑で売買をしてさ やをかせぐ業。旗師。たてあきない。 2餅花 餅を小さく丸め彩色して柳の枝などに 沢山つけたもの。小正月に神棚に供える。黄表紙 「金々先生栄花夢」中に「名に高き目黒不動尊ハ 運の神なれバ、これへ参詣して運のほどを祈らん とまふでけるが、・・・このところの名産、粟餅 ならび(に)餅花といふものあり。 竹をわりて 華鬘(けまん)のごとくにむすび、これニ赤・白・ 黄の餅を花のごとくニつける也。よつて餅花と いふ」の記述あり。 (歌意)開運の神として名高い目黒不動尊の餅花 を食べた植木屋が、運が頼りの旗商い(投機)に手 を出した。あれだけ抜け目のない商いをしていた のに。 |
目黒不動尊 公式ページ |
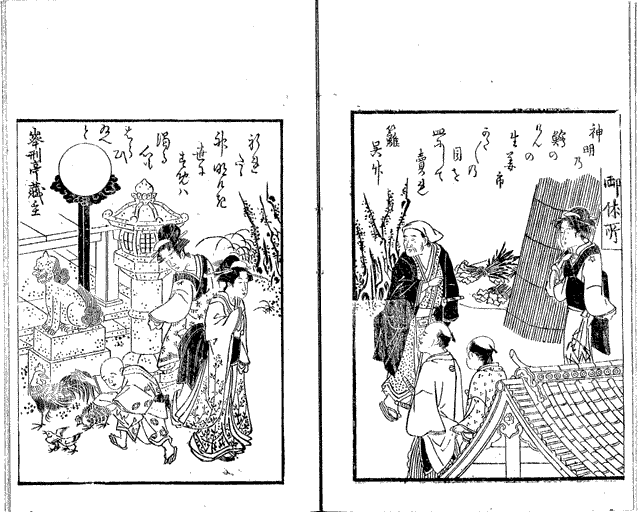 |
(19) 神明の 2生姜市 かたかたの目を 皿にして売れ 籬 呉竹 御休所 祈れたゝ 神 世にすめハ 濁る心も はらひ給へと 崋刑亭 藏主 |
| 芝神明のだらだら祭りはだらだら続く 江戸散策家/高橋達郎氏HP |
1けん 料理のつけあわせ。刺身などのつま。 2生姜市 東京都港区の芝大神宮で、毎年9月 11~21日の祭礼(だらだら祭)に立つ、ショウガ を売る市。 芝大神宮旧称は飯倉神明宮、芝神明宮 |
芝大神宮 公式ページ |
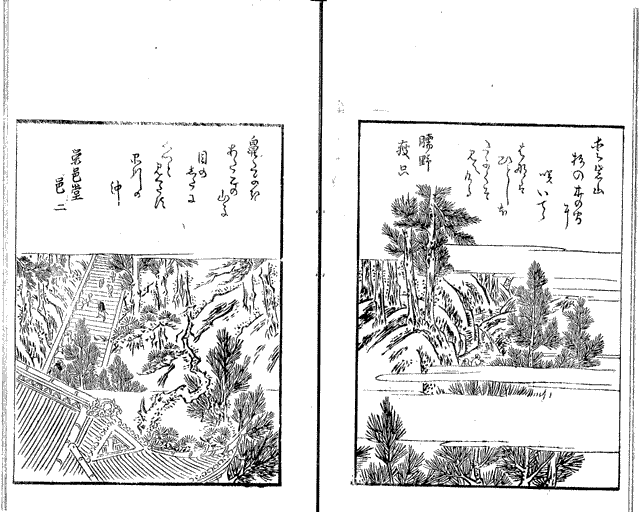 |
(20) 1 杉の木の間に はなは ひとしほ たかくそ見えける 脛野 痩只 鼻たかき あたこの2 目のしたに くいと見くたす 品川の沖 栄邑堂 邑二 |
| 2山子 木樵(きこり)など山仕事をする者の総 称。 |
1愛宕山(あたごやま)東京都港区芝公園 北の丘陵。山上に愛宕神社がある。社前の 男坂の石段は曲垣(まがき)平九郎の馬術で 有名。曲垣平九郎 江戸初期の伝説上の人 物。馬術の達人。名は盛澄。高松藩士。 1634年(寛永11)、江戸愛宕山の男坂の石段 を馬で駆け上り、梅花を手折って、将軍家 光らの賞賛を博したという。 講談「寛永三馬術」などに脚色この故事か ら花は梅の花と思われる。 |
愛宕神社 公式ページ (挿絵左)急な階段は愛宕神社 の正面の坂(男坂)の石段 (出世の石段)。 |
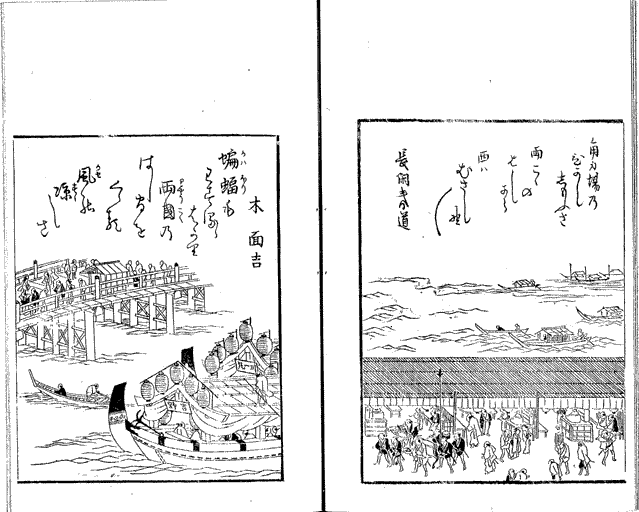 |
(21) ひかし(東)しもふさ(下総) 1両こくの 2はしから西ハ むさし野むさし野 長閑 春道 木 面吉 3 わするゝはかり 両国の はし間をくゝる 風の涼しさ |
|
3蝙蝠(かハほり) |
1両国 東京都墨田区、両国橋の東西両畔の地 名。隅田川が古くは武蔵・下総両国の国界で あったための称。 2両国橋 隅田川に架かる橋で、1661年(寛文 1)完成。1932年鋼橋を架設して現在に及ぶ。 長さ162mル。古来川開き花火の名所。 角力場 両国橋そばの回向院は明暦3年 (1657)大火の犠牲者を弔うために建てられた 寺院で、回向院境内では勧進相撲が明和5年 (1768)~明治42年(1909)旧国技館が完成 するまで行われた。天保4年(1833)からは春 秋二回の興行の定場所となった。 |
両国橋 浮世絵で見る江戸の橋 両国橋界隈 江戸の歴史 江戸最大の盛り場!両国 (挿絵右)両国橋広小路、葭簀屋 根下の賑わいと屋形舟や猪牙 舟の航行する隅田川風景。 (挿絵左)両国橋情景。両国橋の 橋の上の賑わいと提灯飾りと 垂幕をつけた二艘の納涼屋形 船。両国橋をくゞる猪牙舟。 |
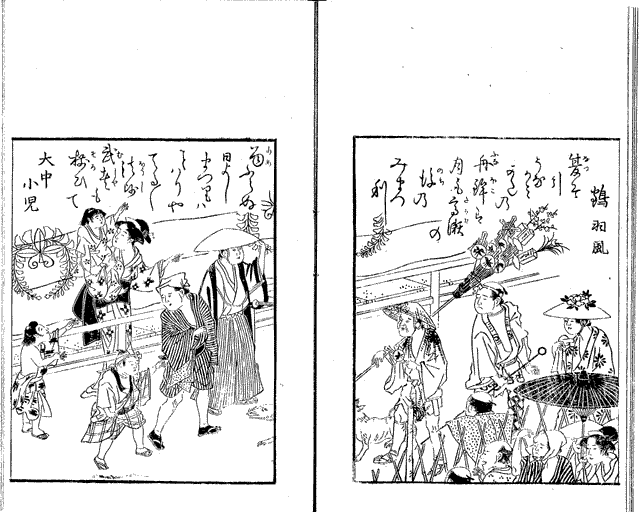 |
(22) 鶴 羽風 1夏そ引 2うなかミかたの 月も高瀬の 雨ふらぬ 3日よしまつりハ ことハりや てるてる法師 武者も揃ひて 大中 小児 |
|
3日吉神社 慶応四年(明治元年)6月以来、 |
1夏そ引 夏麻引(なつそび)く。 枕詞「うな」「い」「命」にかかる。 夏麻は夏に畑から取った麻。 2うなかみかた 海上潟(うなかみかた)
|
日枝神社 公式ページ (挿絵)日吉神社祭り場景。 縁起物の熊手を持つ人、親 子連れ、花笠を被った女、日 傘の女、菅笠の侍や町人達 で賑わう境内。 |
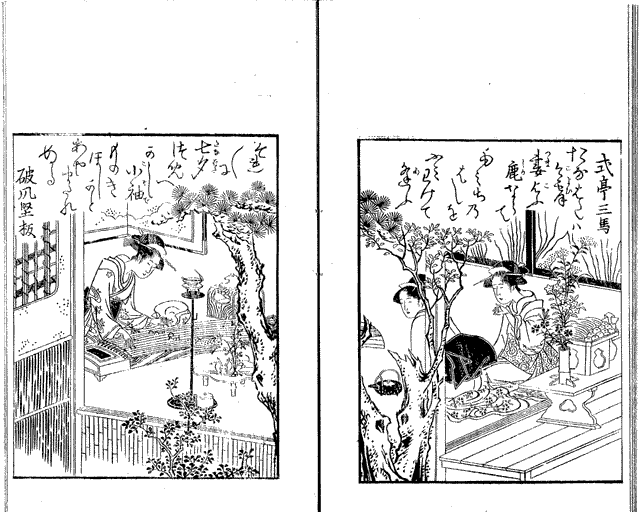 |
(23) 1式亭 三馬 たなはた(七夕)ハ 今宵妻乞ふ 鹿ならて 2もミちのはしを ふミわけて逢ふ それぞれに 七夕つめへ(棚機つ女) かし小袖 3ものきほしかと あやまたれぬる 破風 堅板 |
| 3物着星 爪にできた白い点。女は衣服を得 る前兆として喜ぶ。 |
1式亭三馬(しきてい‐さんば)江戸後期の 草双紙・滑稽本作者。本名、菊地久徳。別号、 遊戯堂・洒落斎など。江戸の人。初め書肆を、 のち薬商を営み、かたわら著作に従事。「雷太 郎強悪物語」を書いて合巻(ごうかん)流行のい とぐちを開く。作「浮世風呂」「浮世床」な ど。(1776~1822) 2紅葉の橋 天の河にわたしてあるという橋 ○天の河もみぢを橋に渡せばや たなばたつめの秋をしも待つ 読み人知らず とあるのに基づく (古今集 四 秋) |
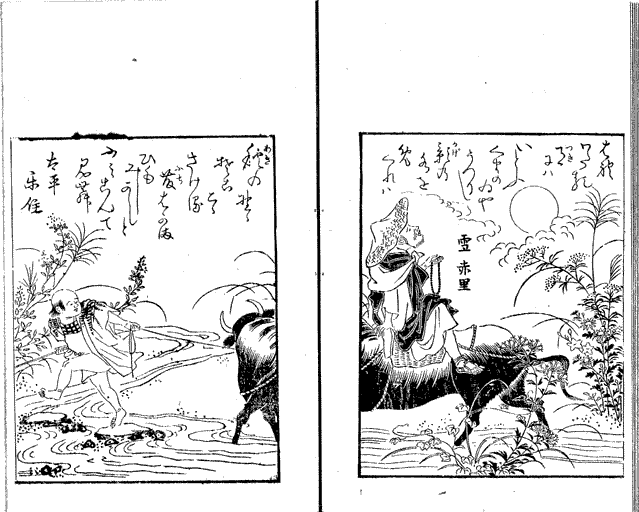 |
(24) はれわたる 月にハ いとふ 1くまのゐや うつりし影の 水をめくれハ 霊 赤星 秋の野の そここゝさける 2藤はかま ひもみしかしと ふミこんて見む 太平楽住 |
| 2藤袴 キク科の多年草。やや湿気ある所 に自生。高さ約1m。下部の葉は三深裂、 全体に佳香がある。秋、淡紫色の小さな頭 花を多数散房状に開く。秋の七草の一。 ○萩の花尾花葛花なでしこの 花をみなへしまた藤袴朝顔の花 (万葉集 八巻1538 山上憶良) ○おなじ野の露にやつるゝ藤袴 あはれはかけよかことばかりも (源氏物語 藤袴 夕霧が玉鬘に藤袴を差 し出して詠いかける) (歌意)秋の野にあちこち咲いている藤袴。 日も短いので踏み込んでよく見てみよう。 (そこここに咲いている藤袴の様によい香 のする女性に一歩踏込んで、粉をかけて みよう。グズグズしてたら日も暮れる。) |
1「くまのゐ」と読むか。 熊の胆 熊の胆嚢から製した薬。その味は苦 く胃及び気附け薬。薬用人参の古称。「お前に 逢ふたは人参熊のゐ」(浄瑠璃 道中双六)。 熊のゐがあげたふおざりいす。どなたでも ちょっと出しておくんなし」青楼小鍋立 享和2年 (歌意)晴れ渡る夜に名月を愛でるには強壮剤 「熊の胆」が重宝される。月影を追って池の水 面をまわれば。(飲み過ぎ、胃のむかつきには 熊の胆を。) |
(熊胆 おくすり博物館) |
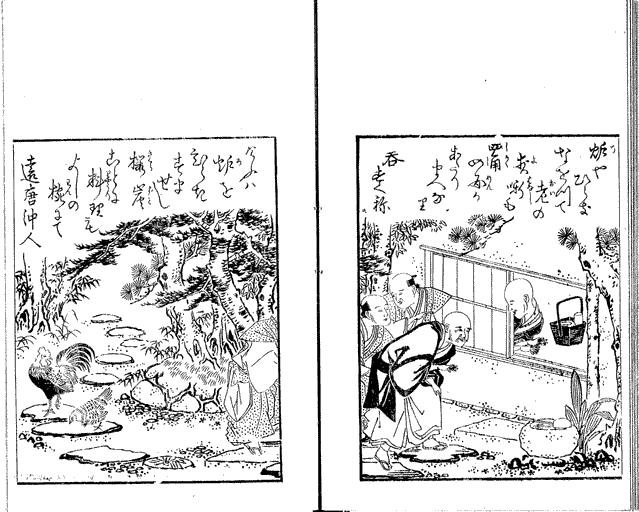 |
(25) 1炉やひらき なをつて老の あたりまへなり 呑 すくね けふハ炉を ひらきすませし 2 ことに料理も 3よしの椀にて |
| 2桜炭 「佐倉炭」佐倉地方で産出する木炭。 クヌギ材を蒸焼きにして製した良質の黒炭。 寛政年間、小金ヶ原周辺で生産しはじめ、 佐倉藩領内で多く産した。 桜と吉野と(料理)よし。 3吉野椀 吉野地方で作られた塗椀。また、 黒漆地に朱、あるいは、朱漆地に黒で芙蓉 (ふよう)を描く吉野絵を表した椀。 |
1炉開き 冬になって炉を使いはじめること。 茶家では、陰暦10月朔日または10月の中 の亥の日に、風炉(ふろ)を閉じて地炉(じろ) を開くこと。「四角」「四面」は「炉」の縁 語。 |
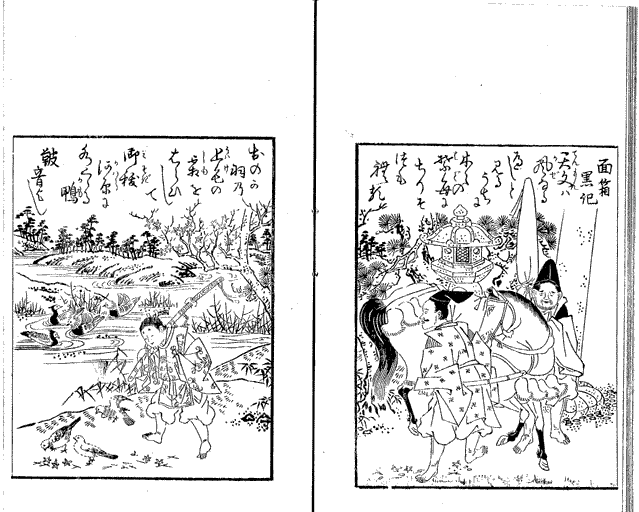 |
(26) 面箱 黒記 天文ハ 風なるへしと 見るうちに 木々の 1ちりそつもれる おのか羽の 霜を 2はらひして 河原に 水くゝる鴨 鞁 音よし |
| 2霜をはらいと禊祓(みそぎはらえ)の祓いを かける。 |
○この里は空かき曇りふる雨に みやまをみれは雪そつもれる (新撰和歌六帖 第一 天 416 衣笠家良) 1散り・塵をかける。天文とちり(地理)で縁語。 |
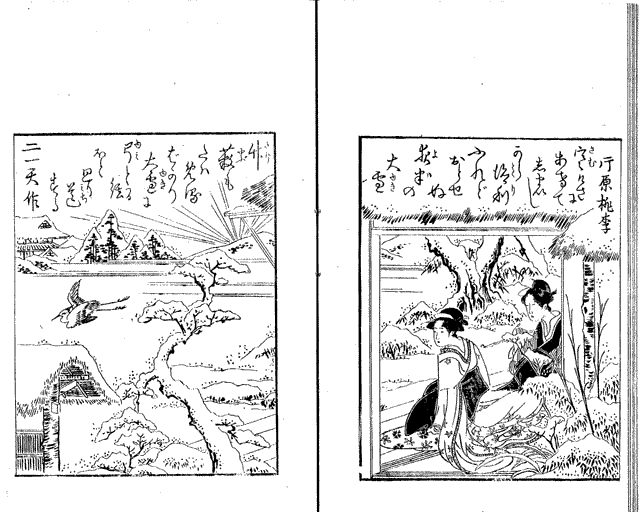 |
(27) 行原 桃李 あけてしまいし から ふれどおとせぬ 大雪 竹薮も たハめるばかり 大雪に 弓と 廻り道する |
| *竹・弓・弦・廻り・たわめる(撓める)縁語。 狂歌名「二一天作の五(にいちーてんさくのご)」 とは、旧式珠算の割算九九の一。一を二で割る 時、この割声を唱えて、一をはらって桁の上 の五を置く。10÷2=5 のこと。 |
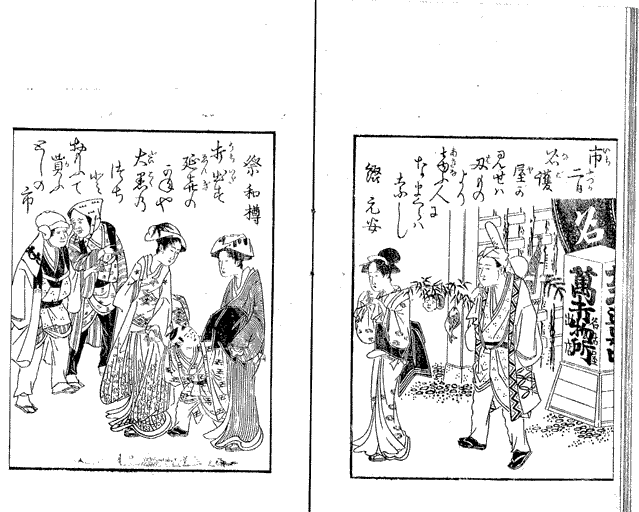 |
(28) 見せハ 1なまくらハなし 2 名古屋 萬打物所 出店 祭 和樽 大黒の つち(槌)と おもふて 買ふとしの市 |
| 3延喜の鐘と大黒様の縁起。 大黒天 七福神の一。頭巾をかぶり、左肩に 大きな袋を負い、右手に打出の小槌を持ち、 米俵を踏まえる。わが国の大国主命と習合し て民間信仰に浸透、「えびす」と共に台所 などに祀られるに至る。 延喜 醍醐天皇朝の年号。 (901.7.15~923.閏4.11) 延喜式 (1)弘仁式・貞観式の後を承けて編 修された律令の施行細則。平安初期の禁中の 年中儀式や制度などの事を漢文で記す。 『延喜式』によれば、2時間おきには太鼓を 打ち、その数は子・午の時にはそれぞれ9つ、 丑・未の時には8つ、責・申の時には7つ、 卯・酉の時には6つ、辰・戊の時には5つ、 巳・玄の時には4つ、また、その間の30分 ごとには、その刻数だけ鐘を撞くと決めら れていた。 |
1なま‐くら(鈍)刃物などの切れ味のに ぶいこと。意気地がなくてなまけもの であること。鈍(どん)なこと。 「名護屋の商人が売る刃物は切れ味がいい が、商人がそれ以上に切れ味が鋭い」と いう意。 2錣(しころ)名前の意は兜(かぶと)の鉢 の左右から後方に垂れて頸を覆うもの。 革または鉄札(てつさね)で綴るのを常と する。 |
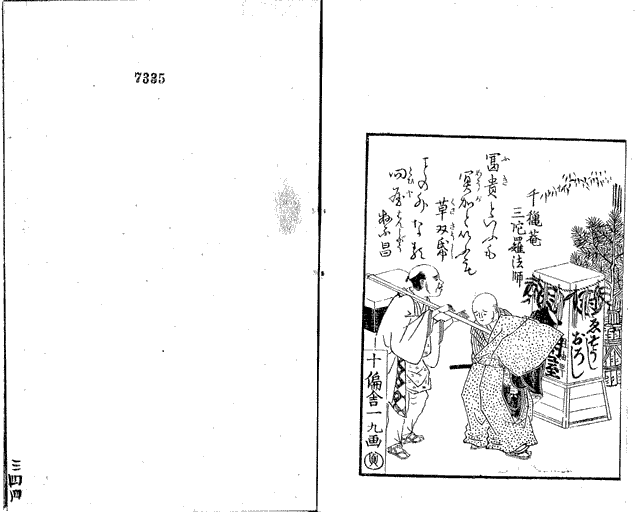 |
(29) 千穐庵 1三陀羅法師 2 3 ことの外なる ゑそうし(絵双紙) おろし(卸) 問屋 十偏舎一九 画 (貞) *文化十年(1813年)刊行 |
| 3草双紙 江戸時代の通俗的な絵入りの読物。 表紙の色や製本のしかたによって、赤本・ 黒本・青本・黄表紙・合巻(ごうかん)など と呼ばれて時代を追って発展。体裁は、 享保(1716~1736)以後、だいたい大半 紙半截(はんせつ)二つ折の中本形、一冊 五丁で数冊を一部とするのが定型となっ ていた。 (歌意)富貴と言うも冥加と言うも、蕗は 富貴に、茗荷は冥加になりますように。 蕗や茗荷のような草々の草双紙。草々が 生い繁るように草双紙も繁昌しますように。 殊のほか問屋繁昌を!
|
1三陀羅法師 1731-1814江戸時代中期- 後期の狂歌師。江戸神田にすむ。唐衣橘洲 (からころも-きっしゅう)の門下といわれ, 千秋側の主宰者となって一派をひきいた。 姓は赤松,のち清野。名は正恒。別号に 一寸一葉,千秋庵。編著に「狂歌三十六歌 仙」「狂歌三陀羅かすみ」など。 なお三陀羅法師とは米俵の両端にあてる、 円いわら製のふたで「さんだら‐ぼっち」 (桟俵法師)をもじった名である。 「さんだらぼうし」ともいう。 2富貴と蕗(ふき)・冥加と茗荷(みょう が)をかける。 |
(挿絵)正月の絵双紙(絵草子) |
|
|