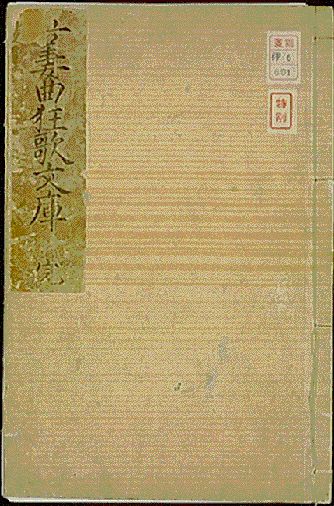 |
(1) |
|
|
北尾政演(山東京伝)画 宿屋飯盛( |
| 別書名 [ 1 ] 天明新鐫五十人一首/吾妻曲狂歌文庫 ( てんめいしんせんごじゅうにんいっしゅ/あずまぶりきょうかぶんこ ) [ 2 ] 五十人一首/狂歌文庫 [ 3 ] 吾嬬曲狂歌五十人一首( あずまぶりきょうか ごじゅうにんいっしゅ ) |
| 解説 狂歌師五十人の肖像に狂歌を添えた彩色刷絵本。狂歌師を王朝歌人風に描いている。 画は 岩瀬 となる。黄表紙「 伝)である。戯作作家として絵師として約四百五十冊もの膨大な双紙を制作した。 撰者は 江戸馬喰町の宿屋の主人で和漢の書に精通、狂歌師中の学者。著は狂歌・狂文に関する 物、他「雅言集覧」「源註余滴」「しみのすみか物語」等約百五十冊。 翻刻に際しては古文書研究家の椿太平氏に、注釈と歌意に関しては福岡在住の松尾守也氏 に多大のご協力を頂きました。厚く御礼申上げます。 画面の解像度は1280×800 ピクセルで作成しています |
|---|
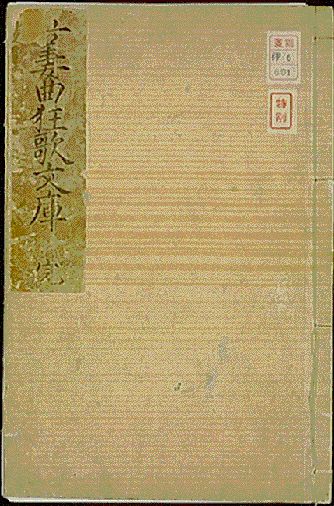 |
(1) |
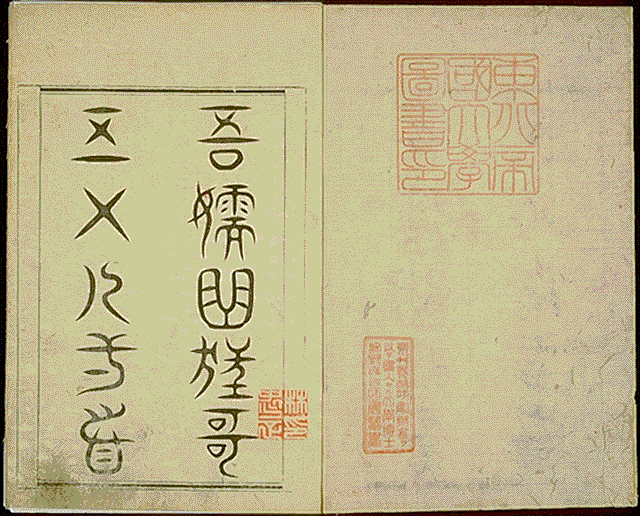 |
(2) 吾嬬曲狂歌 五十人一首 |
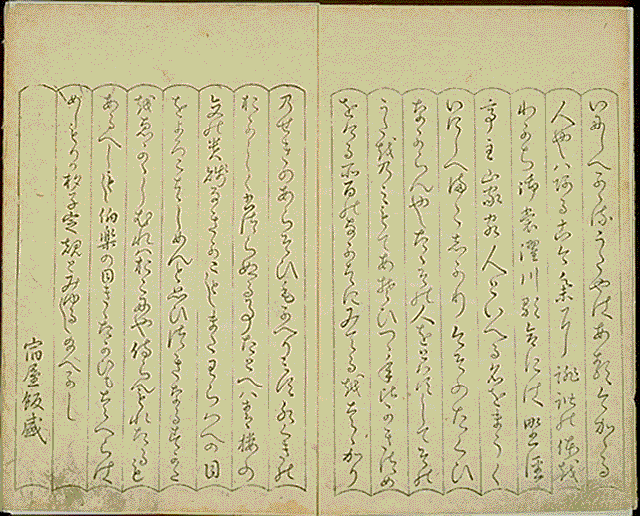 |
(3-1) いにしへかゝる 人やハある。1古今集に2誹諧の体を わかち、3 亭主、山家客人といへる名をまうく。 いにしへまたしかり、今そのたぐひ なからんや。たゞその人をとハずしてその をける所百のなかばにみてるを、5はゞかり の おかしく書つらぬる事、たとへバ6 をよろこばしめんと、思ひつきなるすがた をゑがゝしむれバ、7おこにや侍らん。もれたるも あるべし。もし8 9めしもりの 宿屋飯盛 |
| 1古今集 古今和歌集。 2誹諧の体 古今集(十九巻目)に俳諧の部を初め て設けた。古今集俳諧歌は万葉集巻十六にもある 戯れの歌の系統で一節笑いをふくむものを云う。 3御裳濯川歌合(みもすそがわうたあわせ)西行が 作り藤原俊成が判をした三十六番歌合。 文治3年(1187年) 4野径亭主・山家客人 御裳濯川歌合の中で西行が 使った仮名。 5憚りの関 平安時代陸奥の国、韮神山の下の東街 道(後の奥州街道)にあった関。歌枕。憚りの関 と「憚りの席(遠慮すべき、申し難い席)を掛ける。 ○やすらはで 思ひ立ちにし みちのくの
ありけるものは はばかりの関 後拾遺集 藤中将実方 6水茎 みずみずしい茎の意で筆の美称。筆跡。 「水茎の」「をか(岡)」にかかる枕詞 7青楼 揚屋(あげや)。女郎屋。妓楼。江戸では官 許の吉原を私娼街と区別していう場合が多かった。 遊里で武士も帯刀せずに四民平等の付合いである。 8おこ(痴・烏滸・尾籠)ばか。たわけ。 9伯楽 よく馬の良否を見分ける者。人物を見抜く眼 力のある人。ここでは飯盛等の狂歌仲間、馬喰町連 を利かして洒落ているいる。馬喰の目利きを次の飯 盛の杓子定規こと宿屋飯盛の歌の判断のものさしに なぞらえた。 10めしもりの杓子定規 「めしもり」は次の「杓子」 の縁語。飯盛の意。融通が利かないこと。 |
|
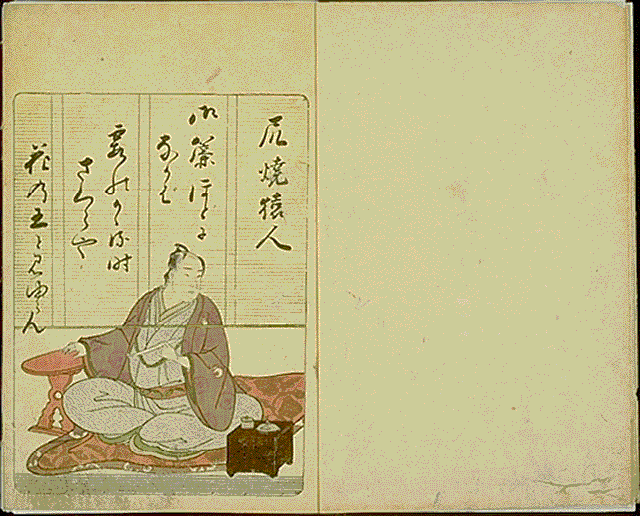 |
(4) 御簾ほどに なかば 霞のかゝる時 さくらや 花の王と見ゆらん |
| (歌意)御簾を通して眺めるように、うっすらと霞 (霞と酒をあたためる湯気)がかかる時、桜はまこ とに美しく、花の王と見えるだろう。 (早く飲みたいものだ。) *霞 春の霞。外に、酒・酢などを熱する時の 湯気。酒の異称。 *桜 古来、花王と称せられ、わが国花とし古くは 「花」といえば桜を指した。 |
尻焼猿人(しりやけのさるんど)酒井抱一(さかいほういつ)江戸後期の画家。抱一派の祖。名は忠因(ただなお)。鶯村・雨華庵と号した。姫路城主酒井忠以(たださね)の弟。西本願寺で出家し権大僧都となったが、江戸に隠棲。絵画・俳諧に秀で、特に尾形光琳に私淑してその画風に一層の洒脱さを加え一家の風をなした。(1761~1828) |
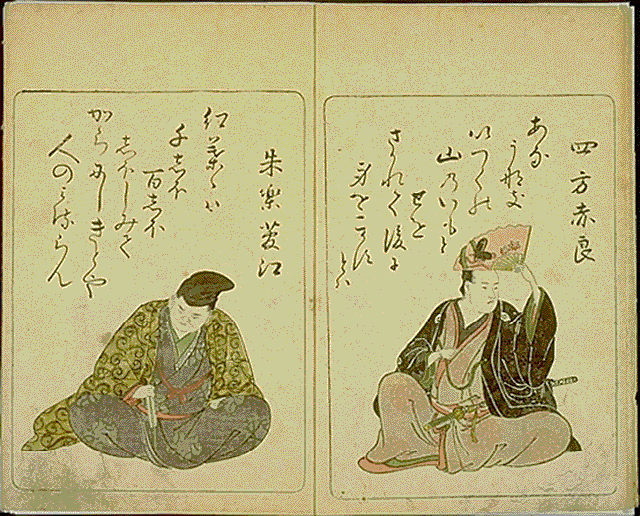 |
(5) あなうなぎ いつくの 山のいもと せを さかれて 身をこかすとハ 紅葉々ハ 千しほ 百しほ しほしみて からにしきとや 人のミるらん |
| (歌意)紅葉の葉は何度も何度も染め釜を 潜らせるうちに華やかな色になり、世間の人 はそれを見て「唐錦」みたいと賞賛するらし い。 (遊女が客を沢山取り、揉まれていくうちに、 以前は「紅葉の葉」のように愛らしかったも のが、今は渡来の「唐錦」のように華やかに なったと世間の人は見て噂をするだろう。) *しお(入)物を染め汁にひたす回数を数える 語。 汐 江戸時代、大坂新町遊里の遊女の階級の 一。太夫・天神・鹿恋(かこい)の次位、影・ 月(がち)の上位。汐以下は、端女郎(はしじ よろう)と総称される。 *からにしき 「唐錦」と「塩がしみたの で辛い」を掛ける。 ○日にも干し風にも干しつ紅に 染むる紅葉の千しほ百しほ 宗良親王千首:秋 490 |
(歌意)ああ、つらいことだな、鰻は。以前は どこかの山の芋だったのに、今は背を裂かれ、 そして焼かれて身を焦がすことになってしまっ たことよ。 (以前は妹・背と呼び合う仲(愛し合う男女の仲) だったのに、今はその仲を裂かれ、互いに恋慕 の情に身を焦がすことになろうとは。情けない ことよ。) *いも‐せ(妹背)愛し合う女と男。夫婦。 妹背山 妹山と背山。 (歌枕)妹背山 和歌山県伊都郡の西、紀の川を はさんで北に背山、南に妹山がある。 ○「山芋が鰻になる」俗説に山の芋は年経て鰻 になるという。(物事が急に意外なものに変 ること) *うなぎの 「背(せ)」に「夫(せ)」を 掛け仲をさかれて。 |
四方赤良(よも‐の‐あから)大田南畝(おおたなんぽ)の別号。江戸後期の狂歌師・戯作者。幕臣。名は覃(たん)。別号、蜀山人・四方赤良・寝惚(ねぼけ)先生。学は和漢雅俗にわたり、性は洒落・飄逸、世事を達観して時勢を諷刺、天明調の基礎をなした代表的狂歌師。狂詩文にもすぐれ、山手馬鹿人の名で洒落本も書いた。著「万載狂歌集」「徳和歌後万載集」 「鯛の味噌津」「道中粋語録」「一話一言」など。(1749~1823) 朱楽菅江(あけら‐かんこう)江戸後期の狂歌師・戯作者。幕臣。本名、山崎景貫。淮南堂・芬陀利華庵と号。著「大抵御覧」「故混馬鹿集(ここんばかしゆう)」など。(1738~1798) |
 |
(6) 千金の花の うハはと ミゆるかな 小粒と なりてふれる春雨 中々に なきたまならば とばかりに かけはたらるゝ 盆のくりこと |
| (歌意)いっそのこと亡霊か精霊になったら、ど んなに楽だろうと思う。溜まった掛金を厳しく 取立てられる盆の繰り言。 *なきたま(魂)は亡き人の魂、精霊。 この歌は詞書きは「盂蘭盆(うらぼん)」 なかなかになきたまなら、の頭韻「な」を連ね る。 ○本歌 なかなかになき魂ならばふる郷に 帰らんものをけふの夕暮れ 正徹 翁草 この歌のパロディー。 *かけはたる (掛徴る・掛債る)借金を徴 収する。 |
(歌意)一分金は千両に比べたらはした金と見 えるだろうな。一分金のように小粒な春雨が 降っている。 (昔は千両の花代を払えたのが今は端金しか 持ち合わせがなくなり、一分金で買える遊女 しか買えなくなった。) *上端 (ウワバとも)(1)物の上部のはし。(2) 端数。特に、金額のはした。 上端 小粒 千金の縁語。 *小粒 一分金。江戸時代の長方形の金貨幣で、 一両の四分の一に当るもの。 |
万象亭(まんぞうてい) 江戸後期の狂歌師・戯作者。本名、森島中良。通称は甫斎。別号、竹杖為軽(たけつえのすがる)など。蘭学者で平賀源内の門人。洒落本「田舎芝居」など多数の著がある。(1754~1808)別号、竹杖為軽(たけつえのすがる)森羅万象一世。 山手白人(やまてのしろひと) 布施弥次郎。名は胤致(たねよし)。幕府勘定所留役。名は山部赤人のもじり。(1737~1787) |
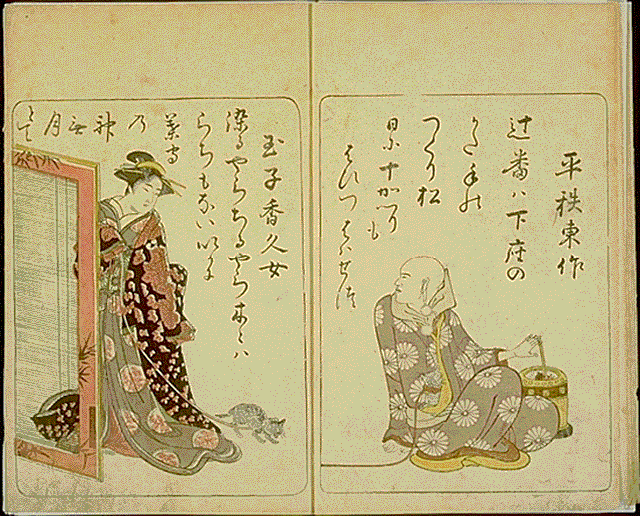 |
(7) 辻番ハ下座の かた手の つくり松 日に十かへりも はひつはハせつ 染るやらちるやら木々ハ らちもない いかに 葉守の 神無月とて |
| (歌意)染めるやら散るやら木々は順序はな い。いかに葉守の神が不在の神無月(十月) だからとて。 (思い込むやら別れるやら女の気々(女心) は滅茶苦茶だ。) ○卵の四角(あるはずのないたとえ) ○埒も無い 順序が立たない。乱雑である。 つまらない。 *染める 深く心をよせる。思い込む。 散る 別れ 木々 気々 |
(歌意)松は千年に十返り(千年に十回花が咲く) するといわれているが、辻番は日に十回も平伏 することはなく、平伏の仕事の片手間に十返り (松)を作っている。 (辻番は暇な仕事だなあ。せいぜい殿様の登・ 下城の二回くらいしか平伏しないじゃないか。 その平伏と平伏の合間には盆栽いじりしかし ていない。) *挿絵は耳から眼鏡を下げ、ふところに猫を入れ ているところ。 *辻番 江戸時代、江戸市中の武家屋敷の辻々 に大名・旗本が自警のために設けた番所。辻 番所。 *下座 座を下りて平伏すること。江戸時代ま で、貴人に対して行なった敬礼。辻番が日に 何度も下座をする片手間に。 *つくり松 松の盆栽 *十返り 十回繰り返すこと。松は百年に一 度、千年に十度花が咲くという伝説からその 花を「十返りの花」という。 「十返りの花」は松の花の雅称。祝賀の意に 用いる。 |
平秩東作(へづつとうさく)立松東蒙(たてまつとうもう)の筆名。江戸中期の儒学者・狂歌師・戯作者。名は懐之。通称、稲毛屋金右衛門。筆名、平秩東作。江戸の人。著「当世阿多福仮面」など。(1726~1789) 玉子香久女(たまごのかくぢよ) 「卵の四角と女郎の誠」の諺による。 |
 |
(8) 思ひきや 十ふの 菅ごも 七ふぐり 女にまけて ひとりねんとは などてかく わかれの 足の おもたきや 首ハ自由にふりかへれども |
| (歌意)後朝(きぬぎぬ)の別れの時の足は、ど うしてこのように重たいのだろうか。首は自 由に振り返れるのに。 (過去をふり返ると別れた女のことが思い 出され、なぜか後ろ髪を引かれることだ。) |
(歌意)思っただろうか。あの十符の菅薦の歌を。 愛しいお前を七符に寝かせ、自分は三符に寝よ うと思っていたのに、だらしなくも女との喧嘩 に負けて七ふぐり、まさかひとりで寝ることに なろうとは。 *十符の菅薦(とふ‐の‐すがごも)編目の十筋 ある菅薦。東北地方の名産。 本歌 ○みちのくの十符の菅ごも七符には 君をねさせて三符にねむ 夫木(ふぼく)集(1310年頃)巻二六雑八 読人不知。 ○おもひきやかかる恋路に入りそめて よくかたもなき歎きせんとは 山家集 西行 *七ふぐり 女に負ける男。女房から尻に敷かれ る亭主。 |
鹿都部真顔(しかつべ‐の‐まがお) (鹿津部とも書く) 江戸 後期の狂歌師・黄表紙作者。通称、北川嘉兵衛。別号、狂歌 堂・四方歌垣。戯作名、恋川好町。江戸の人。戯文を恋川春町に、狂歌を蜀山人に学ぶ。黄表紙「元利安売鋸商内(がんりやすりのこぎりあきない)」など。(1753~1829) 宿屋飯盛(やどや‐の‐めしもり) 石川雅望(いしかわ まさもち)の狂名。石川雅望は江戸後期の国学者・狂歌師。江戸馬喰町の宿屋の主人。和漢の書に精通、狂歌師中の学者。著は狂歌・狂文に関するもののほか、「雅言集覧」「源註余滴」「しみのすみか物語」など。(1753~1830) |
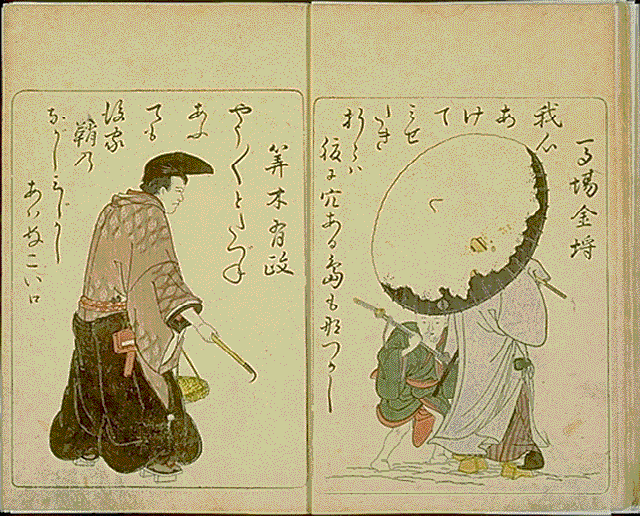 |
(9) 我心 あけてミせたき 折々ハ 腹に穴ある島もなつかし やうやうとたづね あふても 後家鞘の ながしミじかし あはぬこい口 |
| (歌意)やっと訪ねあてても、後家鞘の様に長し 短しだし、鯉口も合わない。 (これはという人にやっと出会えたが、その人は 亭主を亡くした人で、長さも深さも大きさもな かなか合わないものだ。) *後家鞘 まにあわせに使用する別な鞘。 *鯉口 (楕円形で鯉の口に似ているからいう)刀 の鞘(さや)口。 ○帯に短し襷(たすき)に長し 物事の中途はんぱで役に立たないこと。 |
(歌意)疑われて、我が心を開けて見せたい折々 |
馬場金埒(ばば‐きんらち) 江戸後期の狂歌師。通称、大坂屋甚兵衛。初め、物事明輔(ものごとのあけすけ)と号し、のち銭屋(ぜにや)金埒とも。江戸数寄屋橋の両替屋。天明狂歌四天王の一。著に「仙台百首」「金埒狂歌集」など。(1751~1807) 算木有政 さんぎの-ありまさ ?-1794江戸時代中期の狂歌師。江戸京橋にすむ。狂歌師橘実副(たちばなの-みさえ)の兄といわれる。寛政6年3月死去。通称は羽倉則之。別号に常総庵。 |
 |
(10) 春きてハ 野も 青土佐の はつかすみ ひとはけひくや 山のこし張 くひたらぬ うハさも きかず から(唐)大和 たつたひとつの もちの月影 |
| (歌意)不満足と云う噂は唐大和でも聞いたこと がない。すべての人がたったひとつの望月の月 影を堪能している。 (満月の美しさは唐大和でも食い足りぬという 噂は聞いたことがない。しかし、餅の搗かけ や月掛け(=月きめ)の妾では食いたりないな あ。) *○食い足りない 餅にかかる。 望月(満月)に餅をかける。 月影と餅のつきかけと月掛け 月々掛金を出す こと。また、その掛金。 月ぎめで約束した妾(めかけ)。 |
(歌意)春が来て野も青々と青土佐の一刷毛を 引いたように美しく色づく。初霞が山の麓に かゝってまるで腰ばりのようにみえる。 *青土佐(あをどさ) 土佐(高知県)に産する 和紙の一種。紙質厚く、薄い紺色のもの。 *腰ばり 壁・襖(ふすま)などの腰に紙・布 を張たもの。青土佐、腰ばり、ひとはけ、 ひく。紙の縁語のよる見立ての面白さ。 春(はる)・初(はつ)・張り(はり) ひとはけ・ひく 頭韻を揃える。 もちの月影 望月(満月)に餅をかける。 |
腹唐秋人(はらからの あきんど)董堂(とうどう)春星。通称中井嘉右衛門。狂歌を大屋裏住に学び、本町側に入る。狂詩を善くし「本町文砕」の著あり。(1758~1821) 浜辺黒人(はまべ‐の‐くろひと) 江戸中期の狂歌師。江戸本芝に書肆を経営。通称、三河屋半兵衛。1782年 (天明二)「初笑不琢玉(はつわらいみがかぬたま)」を発刊、天明調狂歌集刊行のはじめ。入花(にゆうか)と称する点料の制を創始。(1717~1790) |
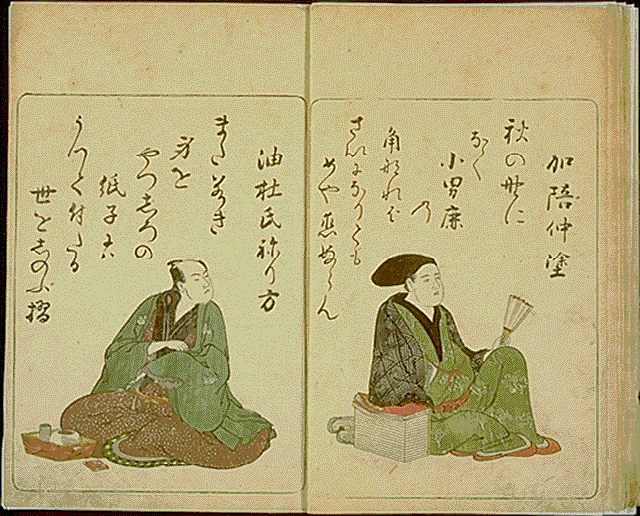 |
(11) 秋の野に なく 小男(さを)鹿 の角なれば さいになりても めや恋ぬらん また若き 身を やつしろの 紙子にハ うつて付たる 世をしのぶ摺 |
| (歌意)まだ若いから、身をやつし、世を忍ぶに は紙子がうってつけだ。白い紙子には信夫摺り がよくつくから。 (この狂歌の背景には衆道がある。この狂歌は 若い相手に贈った恋文で、相手の化粧と着物を 美しいと誉めあげている。) しのぶ‐ずり(忍摺・信夫摺)摺絹の一種。 昔、陸奥国信夫(しのぶ)郡から産出した忍草 の茎・葉などの色素で捩(もじ)れたように模 様を布帛に摺りつけたもので、捩摺(もじずり) ともいう。 ○身を窶(やつ)す。 みすぼらしい恰好をする。 *紙子・紙衣 紙製の衣服。厚紙に柿渋を引き、 乾かしたものを揉みやわらげ、露にさらして渋 の臭みを去ってつくった保温用の衣服。もとは 律宗の僧が用いたが、後には一般にも用い、 元禄(1688~1704)のころには遊里などでも流行 した。かみぎぬ。 |
(歌意)秋の野に分け入り雌鹿を恋いて鳴くさ牡 鹿であるので、その角でつくる采(さい。 賽(サイコロ)は、博打打から目を乞われるよ うに、雌鹿を恋い慕うことだろう。 (男はいつまでも、前の女のことを引き摺っ て、忘れられないものだなあ。) *さ牡鹿の さ牡鹿の分け入る野の意で、「いり の(入野)」にかかる。牡鹿は牝鹿を恋うて鳴 く。 *さい(采)さいころ。「骰」「賽」とも書く。 采の目・賽の目)(1)采の六面に記した一から 六までの目。さいめ。 *こい‐め(乞目)双六(すごろく)などで、ね がい望む *賽(さい)の目。賭博用語。 |
加陪仲塗(かべの なかぬり)江戸中期の狂歌師。通称河合安右ヱ門。師は四方赤良。江戸赤坂に住す。64才。(一般に左官の棟梁なり。故に此号ありと)
(~1832) 油杜氏煉方 あぶらのとうじ-ねりかた 江戸時代中期の狂歌師。江戸数寄屋橋で煉油(調髪用油)をあきなう宇の丸屋の主人。四方(よも)側の社中。天明3年(1783)刊「万載狂歌集」に作品がみられる。 |
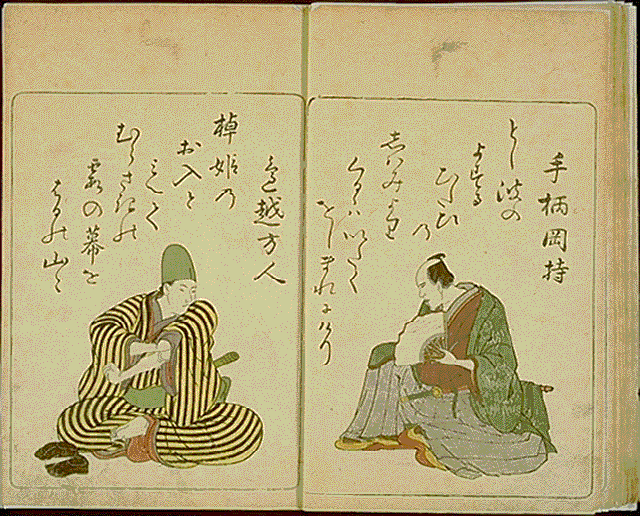 |
(12) とし波の よする ひたひの しハみより くるゝハいたく をしまれにけり 棹姫の お入とミえて むらさきの 霞の幕を はるの山々 |
|
(歌意)春の女神である佐保姫がこの奈良の都に |
(歌意)年を重ねて額の皺が増えるのと、年の暮 れるのは惜しまれるが、御歳暮にものを呉れる のはいたく捨てがたい。 (年を重ねて額の皺の増えることよりも、あの 方はまだ立派なのに使う機会がないのがひどく 残念だ。) *しわみ 皺み。 暮るる・呉るる・くるる くるる(枢) ①「とぼそ」に「とまら」を差込 んで、戸を開閉させる装置。②戸の桟から敷居 に差し込んでとめる木片。=「おとし」。 |
手柄岡持(てがら‐の‐おかもち)朋誠堂喜三二(ほうせいどう きさんじ)の別名。江戸後期の戯作者・狂歌師。本名、平沢常富。別号、手柄岡持など。秋田佐竹藩士。作に黄表紙「文武二道万石通」、洒落本「当世風俗通」、狂歌集「我おもしろ」 など。(1735~1813) |
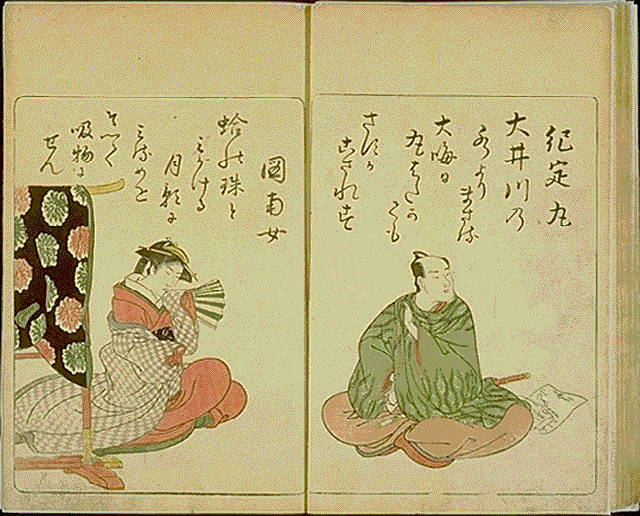 |
(13) 大井川の 水よりまさる 大晦日 丸はたかでも さすか こされす 蛤の珠と ミがける 月影に ミるめを そへて 吸物にせん |
| (歌意)蛤からとれる真珠のように美しく磨かれ た月かげの下で、蛤にみるめ(見た目。容姿と 海松布をかける)を添えた吸物を出しましょ う。 (真珠のように丸く、美しい月の光の下で、蛤 にみるめを添えて口づけをしましょう。) *蛤の珠 蛤貝からも真珠がとれることもある。 真珠の珠のような月。蛤は吸物に使う。特に婚 礼の席の吸物は蛤が定番。 *みる‐め(海松布・水松布)(「め」は海藻の 意) 海松(みる)は海産の緑藻。みるめ。みる な。和歌では多く「見る目」にかけて用いる。 蛤とみるめ(海松布)は隠語。 |
(歌意)大晦日に押し掛けてくる掛取りの圧力 は、押し寄せてくる大井川の水の勢いよりも 凄まじい。丸裸になっても(一銭もなくなって も)その勢いは止められない。 (めぼしい所から借金して払わにゃならん。) *大井川 大晦日 頭韻が同じ。 |
紀定丸 きの-さだまる 江戸時代後期の狂歌師。宝暦10年生まれ。幕臣。大田南畝(なんぽ)(四方赤良(よもの-あから))の甥。四方側に属して天明狂歌壇で活躍し,赤良の狂詩集「通詩選」を校訂。黄表紙「新田通戦記」などもある。文化2年支配勘定,のち勘定組頭になった。姓は吉見。名は義方。通称は儀助。別号に野原雲輔,本田原勝栗など。(1760-1841)。 |
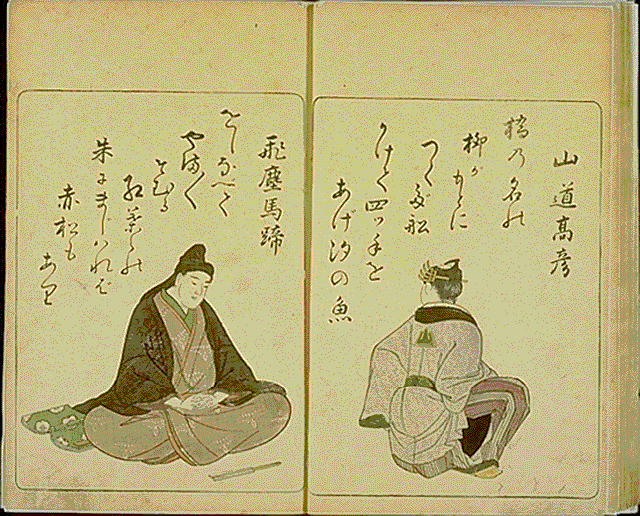 |
(14) 橋の名の 柳がもとに つくだ船 かけて四ツ手を あげ汐の魚 をしなべて やまやま そむる 紅葉々の 朱にまじハれば 赤松もあり |
| (歌意)すべての山々が染まって紅葉の秋。朱に 交わったので赤くなったのだ。その中に赤松も ある。 (吉原の女すべてが紅葉色の装いだ。紅葉の秋 だが、朱に交わったので赤くなったようだ。 その中に私を待っている遊女・赤松もいる。) ○朱に交われば赤くなる」と赤松を掛けた。 松は「松の位」の略。江戸時代、大夫職の遊女 の異称。 |
(歌意)柳橋のたもとに着く佃島通いの船。 そこで四つ手網を上げると、上げ潮に乗って たくさんの魚が獲れた。 (芸者が多く住む柳橋。四ッ手網のように大 きく網をはっていると沢山の男がかかった。) *柳がもと 柳橋のほとり。 *つくだ船「佃島通いの船」と「着く」を掛け た。 *四ツ手(四手網)四隅を竹で張り拡げた方形 の網。水底に沈めて置き、時々引き上げて入 った魚を捕る。 |
山道高彦江戸時代後期の武士,狂歌師。田安家の家臣。江戸小石川牛天神下にすむ。元木網(もとの-もくあみ)の社中に属し,小石川連をおこした。大田南畝(なんぽ)らと交遊があった。文化13年9月10日死去。姓は山口。通称は彦三郎。別号に馬蘭亭,巴蘭亭。編著に「狂風大人墨叢」( ?-1816) 飛塵馬蹄 (とぶちりの-ばてい )江戸時代中期の狂歌師。三卿(さんきょう)のひとつ田安家の家臣で,江戸市ケ谷にすむ。安永年間(1772-81),唐衣橘洲(からころも-きつしゅう),元木網(もとの-もくあみ)らと狂歌会をひらく。作品は「狂歌若葉集」ほかに収録されている。姓は咲山。通称は六郎右衛門。 |
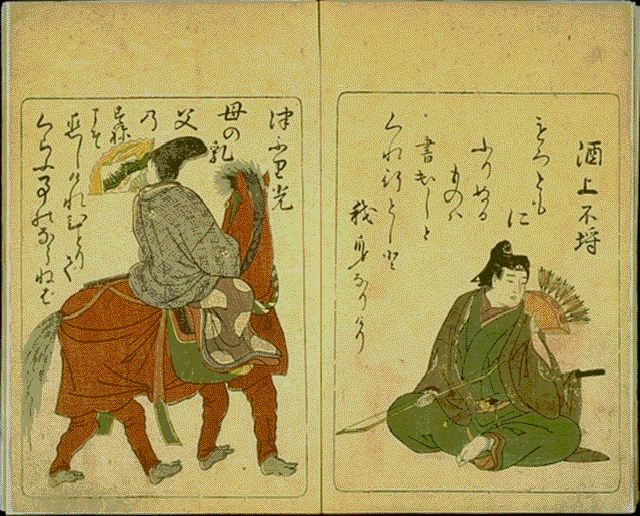 |
(15) もろともに ふりぬる ものハ 書出しと くれ行としと 我身なりけり つふり光 母の乳 父のすねこそ 恋しけれ ひとりで くらふ 事のならねば |
| (歌意)たらちねの母、脛を齧った父が恋しい。 親元を離れたら暮らし向きが容易ではない。 *母のちち(乳) ちち(父)のすね 同音異義語を利かす。 ○親の臑噛(すねかじ)り 子が独立の生活を営 むことができないで、親の扶養を受けている こと。 *くらふ 食らふ。暮らふ。「すね」の縁語。 |
(歌意)そろって疎ましく嫌いになるものは、請 求書の束と迫ってくる年の暮れと、また一つ歳 をとる我が身。 *振る 遊里語。嫌う。はねつける。 *書出 勘定書。請求書。 |
酒上不埒(さけのうえのふらち)。 別号「恋川春町」江戸中期の狂歌師・黄表紙作者・浮世絵師。本名、倉橋格。別号、寿山人。駿河小島の松平家の臣。江戸小石川春日町に住み、恋川春町はそのもじり。「金々先生栄花夢」「高漫斉行脚日記」などにより黄表紙創始者の位置を占め、それらはすべて自画作。(1744~1789) 頭光(つむり‐の‐ひかる) 江戸後期の狂歌師。本名、岸識之。別号、桑楊庵・二世巴人亭。江戸日本橋亀井町の町代(ちようだい)で、狂歌四天王の一人。その社中を伯楽連と称した。(1754~1796) |
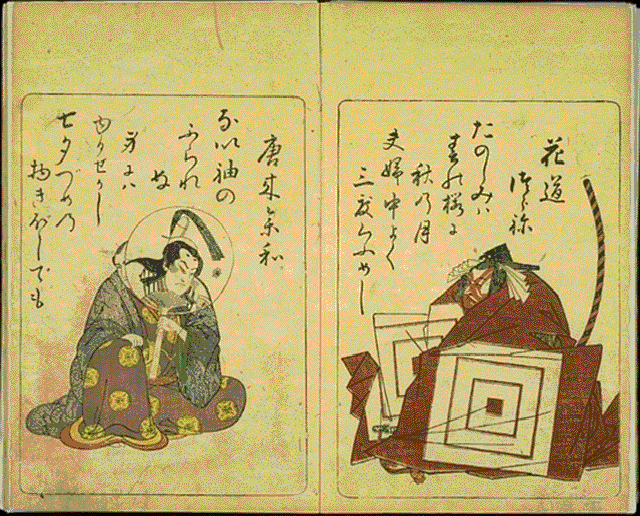 |
(16) 花道つらね たのしみハ 春の桜に 秋の月 夫婦仲よく 三度くふめし ない袖の ふられぬ 身にハ ゆるせかし 七夕づめの 物きぼしでも |
| (歌意)ない袖は振れぬ身の私だから許してくれ。 お前だけでなく、たとえば七夕姫が「爪に物き ぼしができた」と言ってきても、私にはどうも してあげられないのだ。 *七夕づめ(棚機つ女)はたを織る女。秋去姫。 織女星(しよくじよせい)。「爪」の意を掛ける。 *物きぼし 「物着星」でできた白い点。白い斑 点が出来る と女は衣服を得る前兆として喜ぶ。 ○無い袖は振れぬ ないものはどうしようもない。 力になってやりたいが、資力がなくてはどうし ようもない。 |
(歌意)楽しみは春の桜に秋の月。夫婦仲良く 三度食う飯。 *挿絵は歌舞伎十八番「暫」の荒事役(花道つ らね)が「隈取(くまどり)に団十郎家の三 升(みます)の紋を大きく染め抜いた「素襖 (すおう)」に身を包んでいる。 ○楽しみは妻子むつまじくうちつどひ 頭(かしら)ならべて物くう時 「独楽吟」橘曙覧(たちばなのあけみ (1812~1868)の連作全52首を導きだすも の。橘曙覧の「独楽吟」はすべて「たのし みは」で始まり、「とき」(時)で終わる形 式をとっている。この歌は非常に有名な狂歌 とされているが、花道つらねの「白猿狂歌 集」にはなく、四方赤良の「巴人集拾遺( はじんしゅうしゅうい )」に入っているが 実は赤良作であろう。 (小学館日本古典文学全集 黄表紙川柳狂歌) |
花道(はなみちの)つらね 歌舞伎俳優。屋号成田屋。 (五代目市川団十郎。号白猿、俳名三升。寛政期の立役俳優の第一人者。白猿狂歌集著。(1741~1806) 唐来参和(とうらい‐さんな)(名は三和とも書く。拳けんで数を表す語をもじった名) 江戸後期の狂歌師、洒落本・黄表紙作者。加藤氏。通称、和泉屋源蔵。武士の出で、後に町人となり、本所松井町の娼家和泉屋に入婿。狂歌は四方赤良(よものあから)の門。洒落本「和唐珍解」、黄表紙「莫切自根金生木(きるなのねからかねのなるき)」など。(1744~1810) |
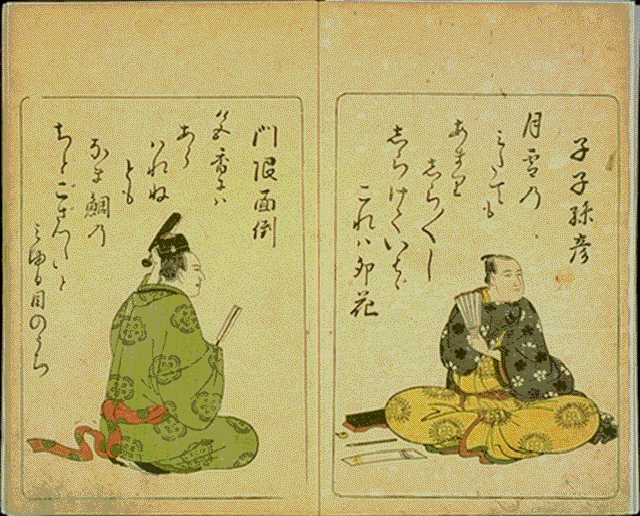 |
(17) 月雪の ミたても あまり しらじらし しらけていはゞ これハ卯花 色香にハ あらハれねとも なま鯛の ちとござつたと ミゆる目のうち |
| (歌意)生鯛は時間が経っても皮や色に変化がない ものの、腐ったかどうかは目を見リゃ分る。 それと同じで、恋心は外には現れないが、目を 見れば分る。ふたごころがあるようだな。 *鯛と他意をかける。他意はふたごころ。浮気 な心。 |
(歌意)月と雪に見立てるとはあまりに白々 しい。白けてこれは卯の花かえ。卯の花とは 憂の花。 *卯の花 (1)ウツギの花。(2)豆腐のしぼり かす。おから。植物の卯の花と安価なおから 料理を掛ける。 雪・卯の花・白々し・白けて。みな白の連 想。 ○卯の花のむらむらさける垣根をば 雲間の月の影かとぞみる 新古今巻三:夏180白河院 ○咲きにけり我が山里の卯の花は 垣根に消えぬ雪とみるまで (元真集 もとざねしゅう)89 藤原元真 |
子子孫彦 このこの-まごひこ 江戸時代中期の狂歌師。江戸小川町にすむ。四方赤良(よもの-あから)(大田南畝(なんぽ))の門人で,天明(1781-89)のころに活躍。姓は村岡。通称は孫右衛門。 門限面倒 もんげん-めんどう ?-1804*江戸時代中期-後期の狂歌師。上野(こうずけ)(群馬県)館林(たてばやし)藩士。江戸日本橋にすむ。四方(よも)側の社中。享和3年12月死去。姓は高橋。通称は徳八。 |
 |
(18) ないて くれ六ツの かねからかぞへ あかすミじか夜 月日をも ふるひつくほど 恋しくて とかくはの根の あハぬ身ぞうき |
| (歌意)震えつくほどに恋して過ごした頃もあっ たのに月日も経てみればとかく歯の根が合わな い身こそ憂きものだ。 *ふるひつく 激しくふるえる。むしゃぶりつ く。「月日経る」と「恋しい」「寒さ」にか かる。 ○歯の根が合わぬ 寒さや恐れのために、震え おののく様にいう。→不協和音 。気心が合 わない。 |
(歌意)ほととぎす一声鳴いておくれ。暮れ六 つの鐘から数えて明け六つまでの短い一夜の 間に。 (ほととぎすの鳴き声を聞こうと初夏の一夜 を過ごしてしまった。) ○なきあかす心地こそすれほとときす ひと声なれとみしかよの空 (新後拾遺集巻七 読人不知)を本歌取りと するか。 *暮れ 鳴いて呉れと暮れ六つの暮れ。 暮れ六つは午後六時頃。季節によって異な る。酉の刻。 |
土師掻安 初号菊泉亭。通称榎本治右衛門。天明年間の狂歌師。(~1788) |
 |
(19) 船出せし うれし涙の水 まして明日ハ ねかハん天のかハどめ うき涙 ふるき 屏風の 蝶つがひ はなればなれに なるぞ かなしき |
| (歌意) 憂き涙。二人の仲が、あたかも岸を離れ て漂う泡沫(うたかた)のように、また古屏風の 蝶番が壊れてばらになるように、そんな風に離 れ離れになることは悲しいことだ。 *(浮き波・憂き涙。涙ふる・ふるき屏風の 「ふる」を掛ける。うき・ふるき・悲しき、脚 韻を踏んでいる) *よたんぼう=酔漢。挿絵の羽織に盃が二つ。 |
(歌意)船出させ恋人に逢えた。嬉し涙が洪 水のように溢れ、明日は川留めになってく れたらいいのに。 (織女星が天の川の川留めを願い牽牛星と 別れたくなかったように。私もしばしこの 逢瀬を重ねたい。) *かわどめ(川留)江戸時代、出水のため、 旅人の川越(かわごし)を禁止したこと。 (天の川・川止め。涙の水と水増し)嬉し 涙を強調する表現。 *てん‐の‐かわ(天の川) 奈良県吉野 郡天川(てんかわ)村にある、十津川の上 流。大峰山から流れ出る。 古歌に「あまのかわ」と詠まれている。 ○七夕のせき止めかたき浪たかな あくれはかへる天の川瀬に (二条為忠家初度百首 秋 292) ○天の川涙の川となりにけり 棚機つ女のけさの別れに (等持院百首 尊氏) |
古瀬勝雄 ふるせの-かつお ?-?江戸時代中期の狂歌師。田安家の家臣。江戸四谷にすむ。酔竹側の社中。天明5年(1785)「狂歌天の川」を刊行。本名は松本保固。通称は亀三郎。字(あざな)は伯厚。画号は花朗斎。 糟句齋(かすくさい)よたん坊 本名;池田いけだ涼岷)?ー? 江戸の絵師;狩野探幽門、水戸藩抱絵師;富坂仲餌指町の水戸藩邸住、狂歌;水戸で狂歌連を結成。別号;余丹坊酩酊、画号;狩野養信・狩野貴信。 |
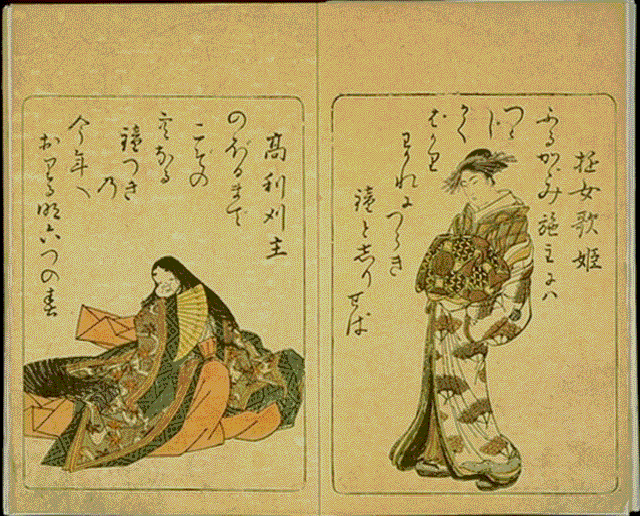 |
(20) ふるかゞみ施主にハ つかじ かくばかり わかれにつらき 鐘としりせば のぼるまで こぞの空なる 鐘つきの 今年へおりる明六つの春 |
| (歌意)日が昇るまでは去年だったが、明六つの 鐘が鳴って新しい年の春になった。 *(江戸時代、時刻制度は日出前と日没の時刻を基 準とする不定時法が行われ、夜が明けだしたこ ろを「明六ツ」と呼び、日没後の空がくれる頃 を「暮六ツ」、そしてこの間を6等分して、 「昼の一刻(ひるのいっとき(=こく))」とした。 一刻の長さは季節により違い、夏はこの一刻が 長く冬は短くなった。 ツꀀ江戸の時刻制度不定時法。 明六つ 明け方の六つ時、すなわち卯の刻。 今の午前六時頃。 「のぼる」「 おりる」。「去年(こぞ) 」と 「今年」。対立する言葉の面白さ) |
(歌意)自分の魂が宿っている古鏡。大切な鏡 を手放すことがこんなにつらいと知っていた なら、私は鏡を寄進しなかったのに。新しい 鐘はつらくて撞くことも出来ない。 *古鏡 梵鐘を鋳(チュウ)するときは、金銭だ けでなく、古鏡や煙管などの銅製品の寄進を 受けるのがしきたり。 *施主につかじ 施主につくとは寄進をするこ と。「撞く」は鐘の縁語。古鏡は「女の魂」 ここでは遊女自身。鐘は「永い間、恋慕して きた相手(=間夫)。永く恋慕してきた間夫と 別れて、その辛さが身に沁みるので、新しい 客につくことができない。 |
遊女歌姫(うたひめ) ? ー? 江戸吉原江戸町松葉屋の遊女、近衛流書道、1784京伝「たなぐひあはせ」序文。 高利刈主(こうりのかりぬし) ? ー? 本所一ツ目御旅所茶屋主人、狂歌;両国連、1785東作「百鬼夜狂」・87才蔵集入; |
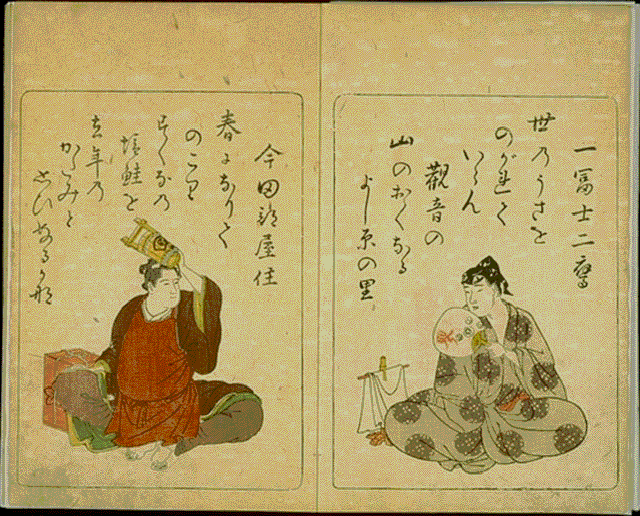 |
(21) 世のうさを のがれていらん 観音の 山のおくなる よし原の里 春になりて のこりすくなの 塩鮭を 去年のかたみと 思ひぬるかな |
|
(歌意)正月になって残り少なくなった塩鮭の |
(歌意)世の憂さや有作(世のしがらみ)から逃 れて人は入るのだろう。浅草観音の山の奥に ある吉原の郭の里へ。 ○よの憂さを なけく心の みにそはは 山の奥にもすまむものかは (新後撰集 巻18 1372 読人不知) を本歌取りしたものか。 *「憂さ」と「有作」を掛ける。 うさ(有作)〔仏〕作られたもの。自然ならぬ こと。有相。 有為〔仏〕さまざまの因縁によって生じた現 象、また、その存在。絶えず生滅して無常な ことを特色とする。(有為の奥山。) |
一富士二鷹 三尺庵。通称藤田甚助。江戸橋本町に住す。四方赤良社中。観音の山の奥浅草寺聖観音宗(天台系の一派)の寺。山号は金竜山。その金竜山の奥に吉原があった。 今田部屋住(いまだへやずみ)田村屋半次郎)狂歌,本所住、1785蔦唐丸催「百鬼夜狂」参、「俳優風わざおぎぶり」/1787「才蔵集」入。 |
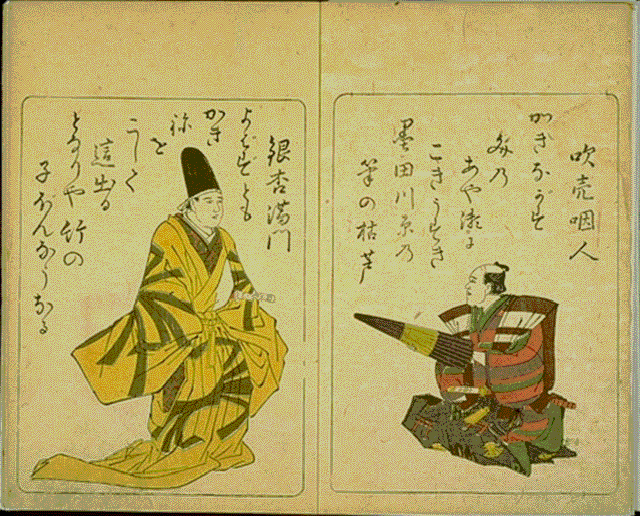 |
(22) かきながす 文のあや瀬に こきうすき 隅田川原の 筆の枯芦 よばずとも かきねを こして這出る となりや竹の 子ぼんなうなる |
| (歌意)隣の家から招かれたのではないが、竹の 子は隣を慕って垣根を越して這い出る。隣は(他 家の子であっても)子煩悩なる人だから。 *竹の子に他家の子をかける。 |
(歌意)さらさらと書かれた恋文の墨色は濃き 薄きを書き混ぜ、熱い想いとつれなさをかき 交ぜて、隅田川原(吉原廓)枯芦の軸の筆で書 かれているな。 *かきながす・書き・文のあや・濃き薄き墨・ 筆。葦手。 散らし書き。文の縁語。隅田川・ながす・あ や瀬・枯芦。川の縁語。 |
吹売咽人(ふきがらのむせんど) 狂歌;深川連、「太の根」初出、1785「後万載」/78「才蔵集」入。 銀杏満門(ちちのみつかど) 銀杏満門(ちちのみのみつかど/いちょうのみつかど、姓;久保/名;九郎太郎、字;百順) ?ー? 幕臣、朱楽漢江・南畝と親交、江戸牛込二十騎町の狂歌作者;山手連/朱楽連、南畝「後万載集」/狂歌鶯蛙集入。 |
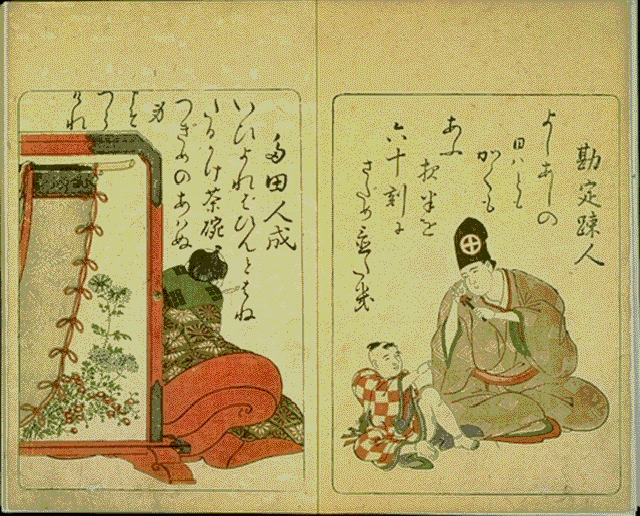 |
(23) よしあしの 日ハとも かくも あふ夜半を 六十刻に さだめ置たき いひよればひんと はねたるかけ茶碗 つぎめのあハぬ 身こそつらけれ |
| (歌意)言い寄ってみれば肘鉄砲を喰らってしま った。相手と反りが合わない自分はつらい。 (口説いてみれば肘鉄喰らったが、女は茶碗で キズモノ。相手に合わせられない自分がつら い。) *言い寄ればぴんとはねたる。 茶碗の欠ける」と「はねつける」(拒絶する) を掛ける。 茶碗 隠語。「かわらけ」とも。 |
(歌意)善いも悪いも、ともかく恋人に逢ふ夜 は時間を六刻を倍の六十刻に定めて置きたい ものよ。 (吉原の恋しい女に逢う夜は、どんな日であ っても、六刻(約十二時間)を十倍の六十刻に 定めて少しでも長く一緒にいたいものよ。) *六十刻 夜中は子の刻から卯の刻まで六刻 であるが十倍して夜を長くしたい。 |
勘定疎人 花島平蔵。深川に住む。 絵双紙屋「絵本詞の花」「「絵本 譬喩節」に狂歌がみえる。 |
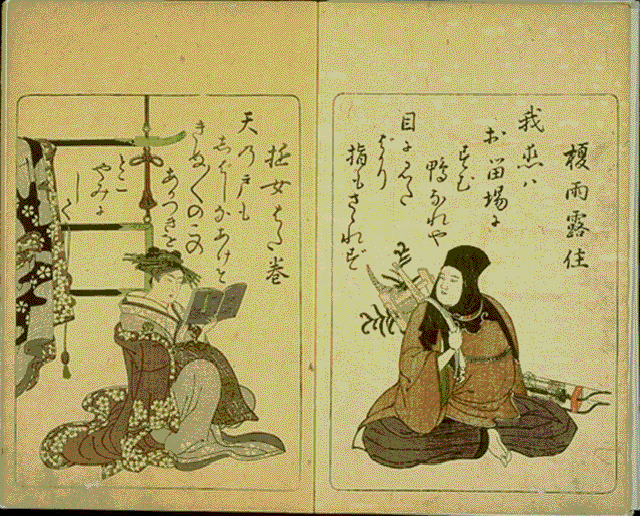 |
(24) 我恋ハ お留場に すむ 鴨なれや 目に見た ばかり 指もさゝれず 遊女はた巻 天の戸も しばしなあけそ きぬぎぬのこの あかつきを とこやみにして |
| (歌意)天の岩戸を今しばし開けないで。後朝 の別れをしなくてすむように、ずっと闇にし ておいて。 *天の戸 天の岩戸と遊郭の部屋の戸。 *とこやみ 「常闇」と「床」を掛ける。 |
(歌意)我が恋は禁猟区の鴨を相手にしてるよ うだ。ただ眺めるだけで指も触れられず。 (惚れた女(遊女)は格子窓越し。遊ぶカネもな いので、ただ眺めるだけ。) *お留場 一般の狩猟を禁止する場所。将軍家 や寺社用の禁猟地区。 |
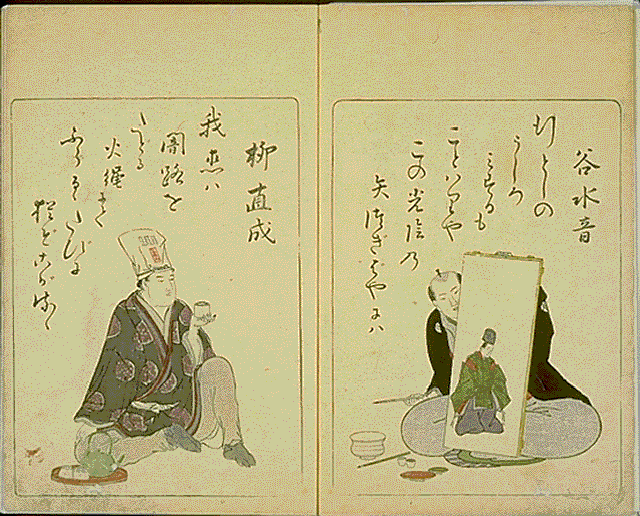 |
(25) 行としの うしろ ミするも ことハりや この光陰の 矢つぎばやにハ 我恋ハ 闇路を たどる 火縄にて ふらるゝたびに 猶ぞこがるゝ |
| (歌意)わが恋は闇夜をたどる火縄のようだ。 火縄を振るとよく燃えるように、女にふられる とますます恋いの炎が燃え上がる。恋は闇路。 無分別の世界へ我が身を焦がす。 *火縄にてらるゝたび 火縄を振るとよくもえ る。 *おけら‐まつり(朮祭・白朮祭)京都八坂神社 で大晦日から元 旦にかけて行う神事。鑽火(き りび)で朮を交えたかがり火を焚き、参拝者はそ の火を火縄に移して持ち帰り雑煮を煮る。 |
(歌意)自分の過ぎ去った歳月をふり返ると、こ の光陰の矢継早さにおどろくばかり。 (我が後胤が続けざまに生まれた。行く末まで 世話(後見)するのは道理というものだろう。) ○光陰矢のごとし 「光陰」と「後胤」をかける。 行くとし 「過ぎ去る年」と「行く末までの 年」光と陰は対語。 「後見する」「矢継ぎ早」ともに弓矢をとる武 士の縁語。 |
1谷水音(たにのみずおと) 江中期甲府の絵師;三輪花信斎門?、狂歌・橘州門(俳優風)、「狂歌才蔵集」・新玉集入。? ー? 柳直成 やなぎの-すぐなり 江戸時代中期の狂歌師。上野(こうずけ)(群馬県)高崎の商人。天明のころの狂歌壇のひとり。当地の名人と称された。姓は鈴木。通称は庄七,のち治兵衛。 |
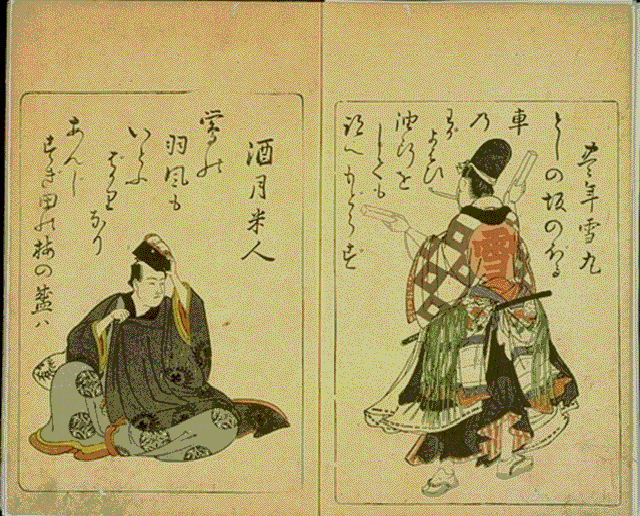 |
(26) としの坂のぼる 車の わがよはひ 油断を しても 跡へもどらず 鴬の 羽風も いとふ ばかりなり あんじ すぎ田の梅の盛ハ |
| (歌意)鴬の羽風にも花が散るのではと案じ過ぎ るくらい案じたものだった。 杉田の梅の盛りは。 *杉田の梅 横浜市の南部、磯子の梅林。 案じ過ぎと杉田の「すぎ」をかける。 ○鴬の羽風もつらし桜花 散りのみたれに春やゆくらむ (洞院摂政家百首 春 202 道家)を本歌と するか。 |
(歌意)年の坂、のぼる車の私の齢は油断しても 決して後へは戻らず。歳月は人を待たずだ。 |
豊年雪丸.松月庵・月花園と号す。尾張名古屋の人.通称は市橋助右衛門。狂歌を唐衣橘洲に学びて同門中に傑出す。安永二年始めて尾張に仕へて,勘定方並に手代となり俸を賜ふ。後勘定本締役,記録所書役となり、班を歩行格に列す。(~1821) 酒月米人(さかづきのこめんど)狂歌作者。通称は榎本治兵衛。江戸本町に住んだ。のち霊岸島塩町に居を移し,榎本(扇屋とも)三右衛門と称した。別号は狂歌房,吾友軒。狂名は,酒盃では献酬が小面倒だというのに由来するか。天明3年ごろ四方赤良の門下となり、寛政以後四方側の有力判者になる。和文にも巧みで南畝が寛政11年に始めた「和文の会」の一員となり南畝編『ひともと草』に4編の短編が収録されている。?-? |
 |
(27) うハかハの 目もとに しほハ こほるれと たゝ心中の 水くさきかな ふた声と きかでぞ 沖を はしり船 なごり をしさの 山ほとゝぎす |
| (歌意)ほととぎすの声を一度しか聞かないう ちに、帰りの猪牙舟は吉原から漕ぎ出し、走 るように隅田川を下っている。名残惜しいこ とよ。 (ほととぎすをもっと鳴かせ、鳴き声をもっ と聞きたかった。) ○二声と聞かずば出でじ郭公 いくよあかしのとまりなりとも 新古今集 藤原公通を本歌とするか。 *本歌の「幾夜明かし」の「明かし」と「明石 の泊」の「明石」」とが掛詞。「沖をはしり 船」と表現しているが、裏の意は吉原から乗 った猪牙舟が隅田川を下っているさま。 猪牙舟は船体が細く、速力が出たので「走 る」と表現している)。 (浅草の山の奥にある所(=吉原) で鳴くから「山ほととぎす」。 山時鳥は昨夜鳴(=泣)いた遊女。) |
(歌意)うわべは上瞼の目元に愛嬌があふれて いるのだが、ただ心の中はよそよそしく水く さいことだなあ。 (美人には見えないが、その目元には愛嬌が あるから、伝説の姥皮を着ているのかもしれ ない。しかし私に対して心を開いてくれない のは水くさいなあ。) *うはかわ(上側) 上になっている側。 表面。外面。うわべ。また、みせかけ。 *姥皮 身に着けると老女の姿になるという 想像上の衣。脱ぐと、もとの美男か美女の 姿に 戻り、幸福になるとされる。 姥皮(蛇婿~退治型) *しほ (潮・汐)愛嬌。情趣。 しぼ しわ(皺)。 かは、しほ(汐の流れ)、こぼる(零る・ 溢る)は水の縁語。 *当時流行の伊勢音頭の一節が利用されている。 ○あの君様は伊勢の浜育ち 目元にしほがこぼ れかかる 寛永十二年跳記 ( おどりき ): 『古今夷曲集』『後撰夷曲集』『銀葉夷歌集』 の手法について 大阪府立大 黒木 祥子氏 |
小川町住(をがはまちずみ) 讃岐高松藩士。通称大高仁助。 |
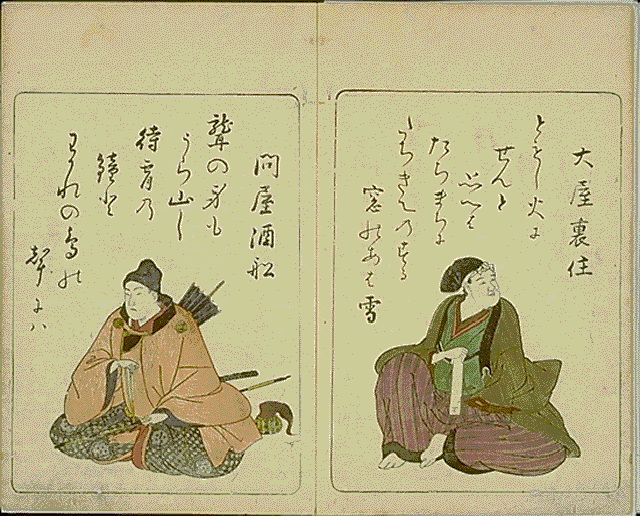 |
(28) ともし火に せんと 思へは たちまちに たちきえのする 窓のあは雪 うら山し わかれの 鳥の声にハ |
| (歌意)耳の不自由な人も羨ましい。待宵の鐘の音 も、後朝の別れの鳥の声も聞こえないのだから。 (鐘の音を聞きながら、「いまか、いまか」と 待っていた。やっと逢えても、すぐに鳥が鳴き、 別れの朝がくる。鐘の音も鳥の声も聞こえない 人が羨ましい。) *「みみしい」と「身(み)」頭韻が同じ。 「羨まし」「裏山寺」をかける。 浅草寺裏に吉原の遊郭があった。 待宵の相手は遊女か。 *待宵(まつよい) ①訪れて来るはずの人を待って いる宵。②(翌日の十五夜の月を待つ宵の意)陰 暦八月十四日の宵。 ○待宵のふけゆく鐘の声きけば あかぬ別れのとりはものかは 太皇太后宮小侍従 新古今集 上記の歌を本歌取りしたものか。 うら山し 裏山路。羨まし。 |
(歌意)蛍雪の功の故事にならって、積もっ |
大屋裏住(おおや‐の‐うらずみ)(1734~1810)は久須美氏,通称は白子屋孫左衛門、別号を窓雪院。初めは更紗屋であったが,明和年間より江戸日本橋金吹町に住んで貸家業を営んだ。狂名はその家業による。寛延年間より卜柳の門に入り,初めの名を大奈権厚紀といった。その後二十余年間,狂歌を離れていたが,明和年中,再び活動を始め,四方赤良(大田南畝)に従って大屋裏住と号した。天明ごろから手柄岡持、酒上不埒(恋川春町)らの属した本町連を主宰した。 問屋酒船 通称井上幸次郎。東都南 新堀に住す。 |
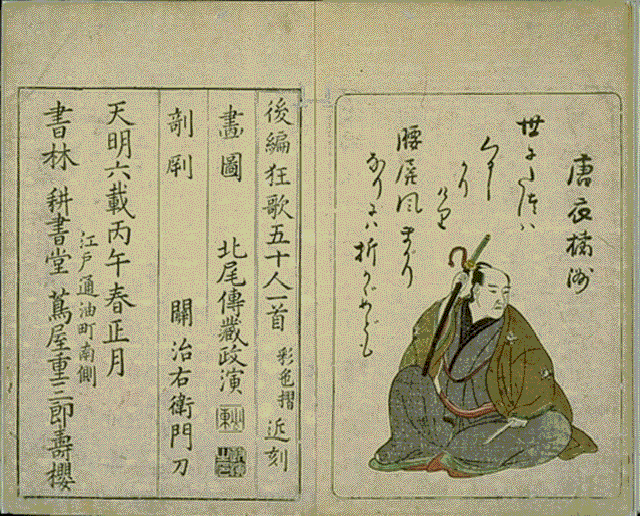
| (29) 世にたつハ くるしかりけり 腰屏風まがり なりにハ折かゞめども 後編狂歌五十人一首 彩色摺 近刻 画図 北尾傳蔵政演 剞判 関治右衛門刀 天明六載丙午春正月 江戸通油町南側 書林耕書堂 蔦屋重三郎寿桜 |
| ○世に立つ 一人前の人間として世間に 出る。また、出世する。 「たつ」「まがり」「折り」は「腰」は 「屏風」の縁語。 *まがりなりに 十分とまでは行かないが。 どうにかこうにか。 *折かゞめ 礼儀を尽くして謙る。 |
(歌意)この世で生きていくことは難しい。まして 出世をすることは苦しいことだ。腰屏風のように、 腰を折り屈めてぺこぺこお辞儀をしながらどうに かこうにか生きている。 (腰は曲がりなりにも腰屏風のように折り屈める けれども、年を取ったことだなあ。夜に立つのが 難しくなったことよ。) |
唐衣橘洲(からごろも‐きっしゅう) 江戸後期の狂歌師。幕臣。小島謙之(よしゆき)。号は酔竹庵。江戸の人。四方赤良(よものあから)・朱楽菅江(あけらかんこう)と共に狂歌中興の祖。作風は温雅・軽快で、天明調の先駆。著「明和十五番狂歌合」「狂歌若葉集」など。(1743~1802) 北尾傳蔵政演 山東京伝のこと |
|
|
表紙へ 目次へ ページ最上段へ 古今狂歌袋 宿屋飯盛撰 北尾政演画 絵本 詞の花 喜多川歌麿画 宿屋飯盛序 和泉屋源七板 江戸名所図会 十返舎一九画 |