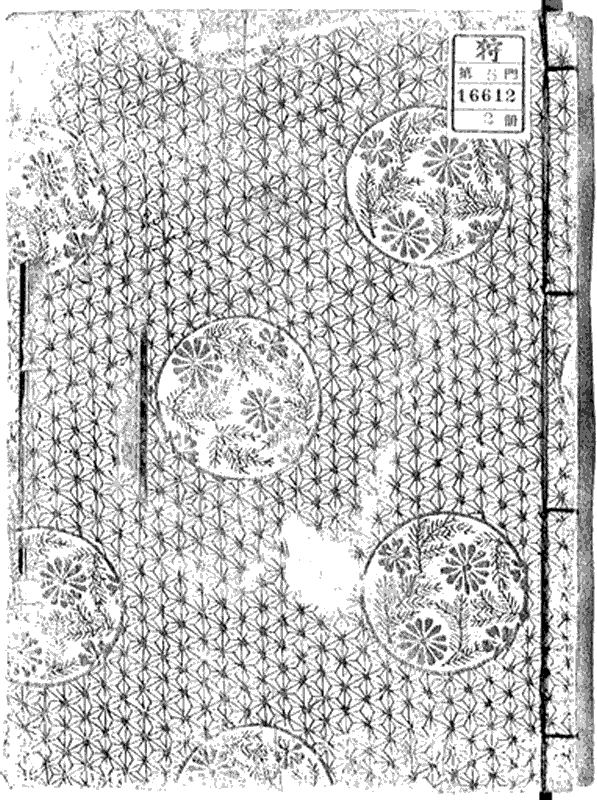 |
絵本譬草 下巻 |
| 2020/3/3 改訂 表紙へ 目次へ |
|
「絵本譬草 上巻へ」 |
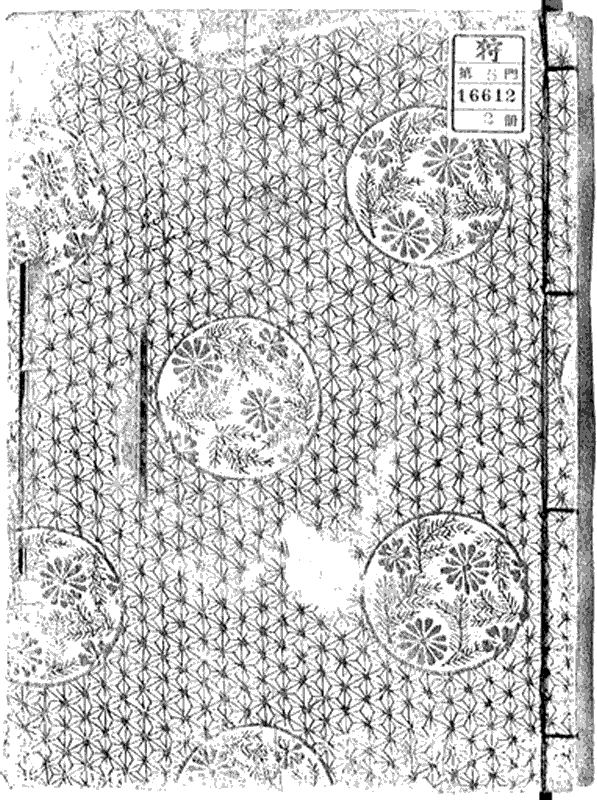 |
絵本譬草 下巻 |
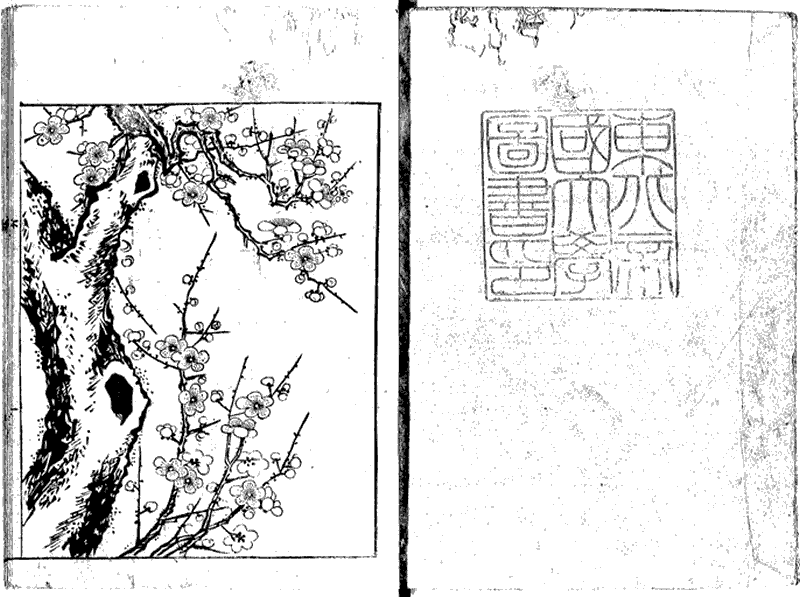 |
(1) |
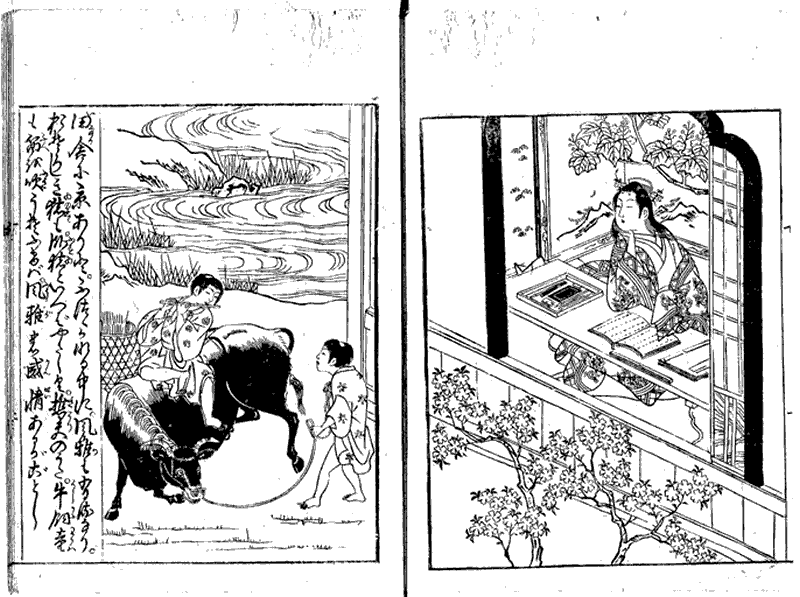 |
(2) (風雅はいたるところにあり) 田舎に京ありと。1ふつゝかなる中に。風雅も有るなり。 おそろしき猪も。 も笛を |
| *ふつつか(不束) やぼったいこと。 臥猪 ねているいのしし。絵本徒然草(第十四段)参照 (絵双紙屋HP) |
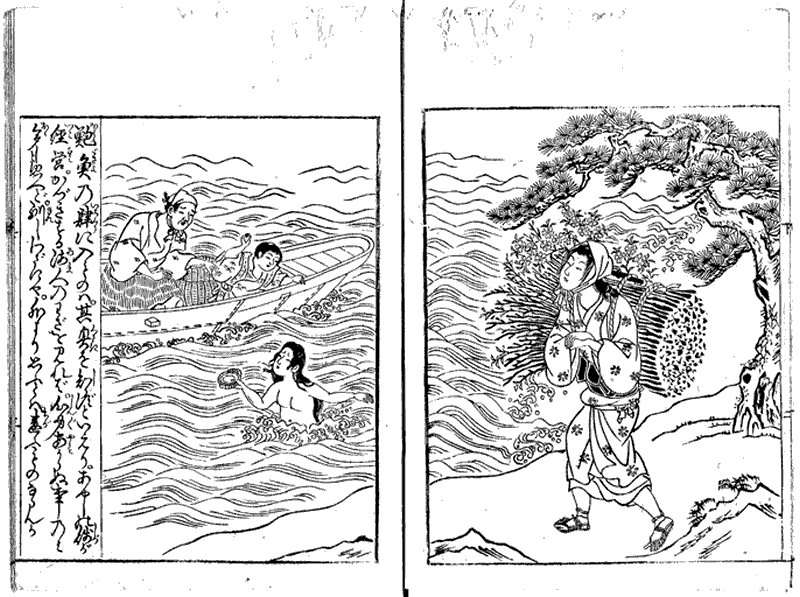 |
(3) ( 多しと思へど。馴しわざにや。外より思ふとハ。違ふことのなるんか |
| ○鮑魚の肆(いちぐら )[孔子家語六本「与不善人居、如入鮑魚之肆」] *不善の人、小人などの集まりを塩漬の臭い魚を売る店にたとえていう。 かづき(潜き)水中にもぐって貝・海藻などを取る。 万十一「伊勢のあまの朝な夕なに潜くとふあはびの貝の片思(もひ)にして」 |
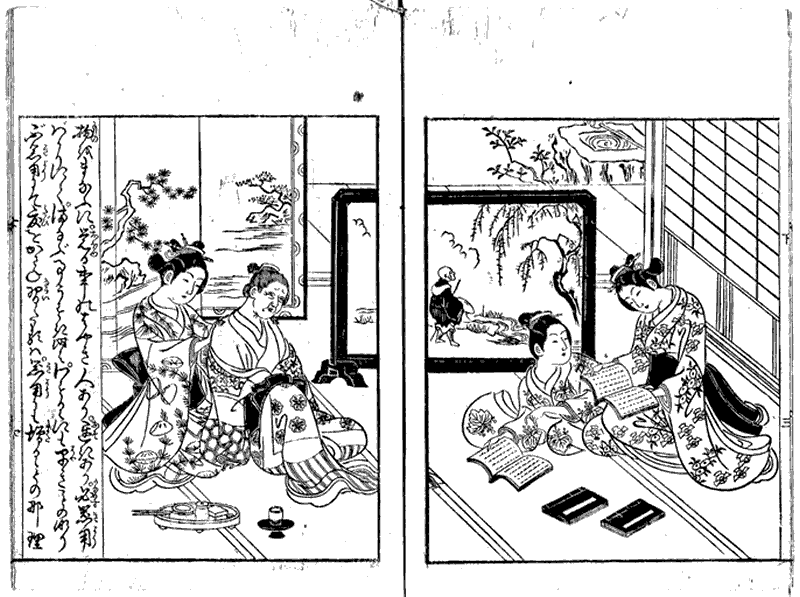 |
(4) (学びは不器用でも努力で 身に付く) 物をまなふに。覚る事のはやき人あり。遅きあり。 バかりにて。まなぶ事うすき内は。わするゝにも早きものなり。 ぶ器用にて |
| ○器用貧乏 なまじ器用なために、あれこれと 気が多く、また都合よく使われて大成しないこと。 重宝がられる) ○早合点の早忘れ 早のみ込みは当てにならないこ と。 ○早かろう悪かろう |
○大器晩成 [老子第四十一章「大方無隅、大器晩成」] 鐘や鼎(かなえ)のような大きな器は簡単には出来上が らない。人も、大人物は才能の表れるのはおそいが、 徐々に大成するものである。 |
|||
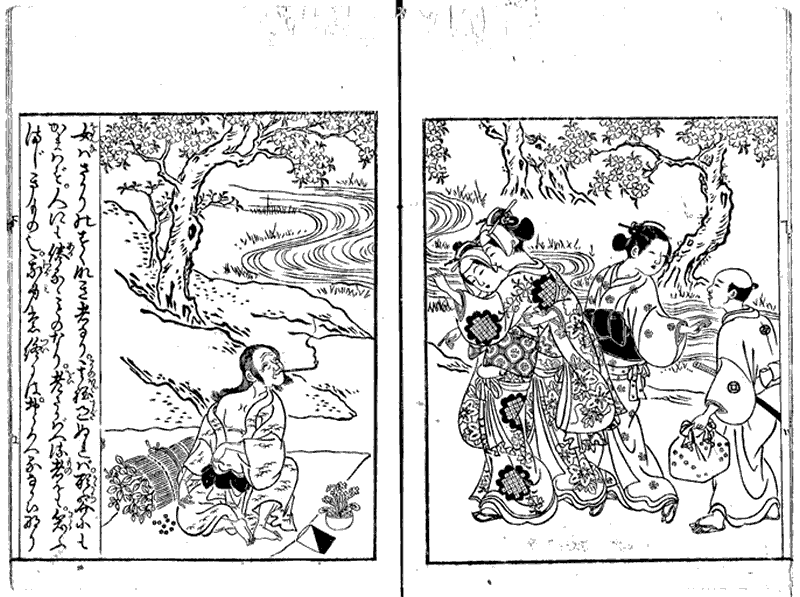 |
(5) (女は身だしなみが大切) 女ハさかりのすくなき者なり。其程過ぬれバ。 かまハず。人にも まじきもの也。我身も |
| ○花の色は 移りにけりな いたづらに 我が身世にふる ながめせしまに (古今集 巻二 春下 113 小野小町) 女の容色は花の色のように衰えやすいものという。 |
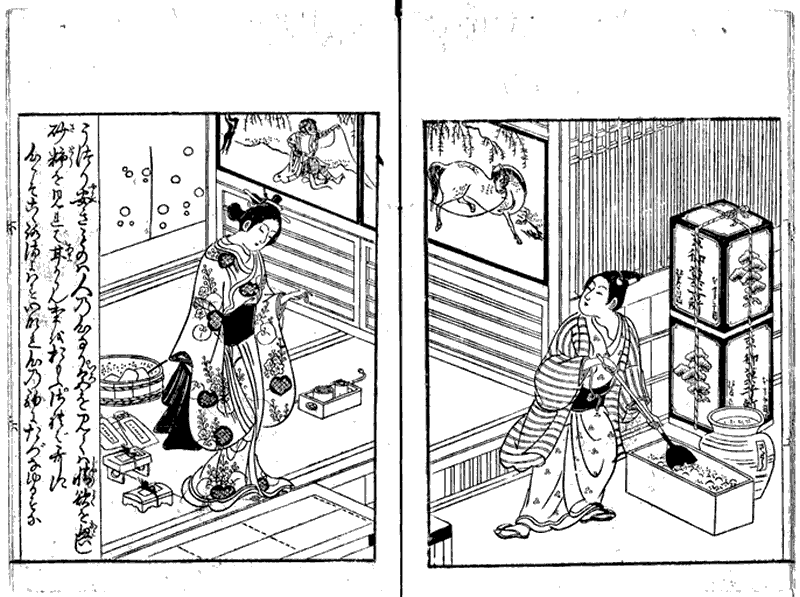 |
(6) (人の心は移ろいやすいもの) うつり安きものハ人の心なり。色も見てハ情欲を愛し 砂糖を見れば。甘からん事をおもふ。されば歌に 心こそ心 |
|
○色見えてうつろふ物は世中の |
*心の駒 心の馬 (「意馬」の訓読) 情意の制し がたいことを馬にたとえていう語。 |
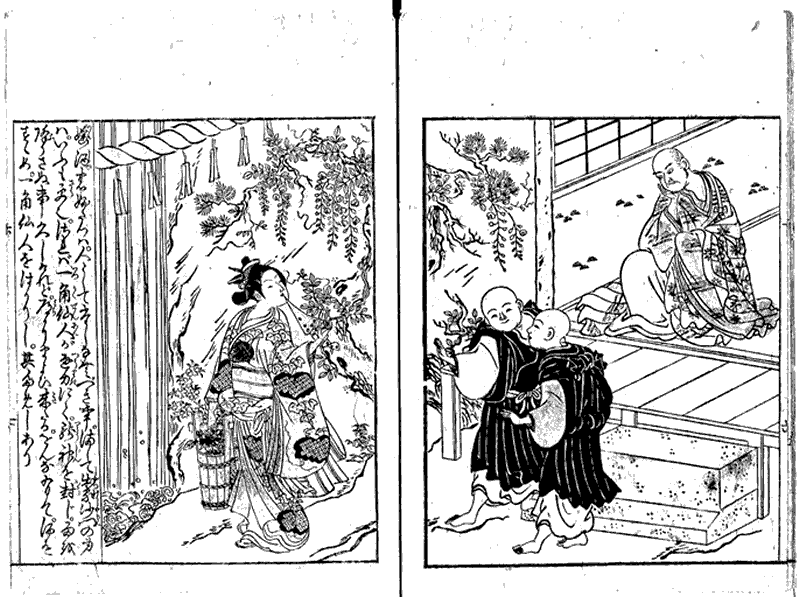 |
(7) (淫らとお酒は注意) ハ。いふも更也。されバ一角仙人が通力にて。龍神を封じ。雨を 降らさぬ事久しけれど。道にまよひ来たる。をんな有て。酒を すゝめ。一角仙人をはかりし。其ためしあり |
||
| *一角仙人 インド波羅奈国の山中で鹿から生れ、頭に一角 があったという仙人。 長じて禅定を修して通力を得、国王に恨みを抱いて雨を降ら さなかったが、国王の遣わした淫婦に惑わされて通力を失い、 雨を降らしたという。 |
|
||
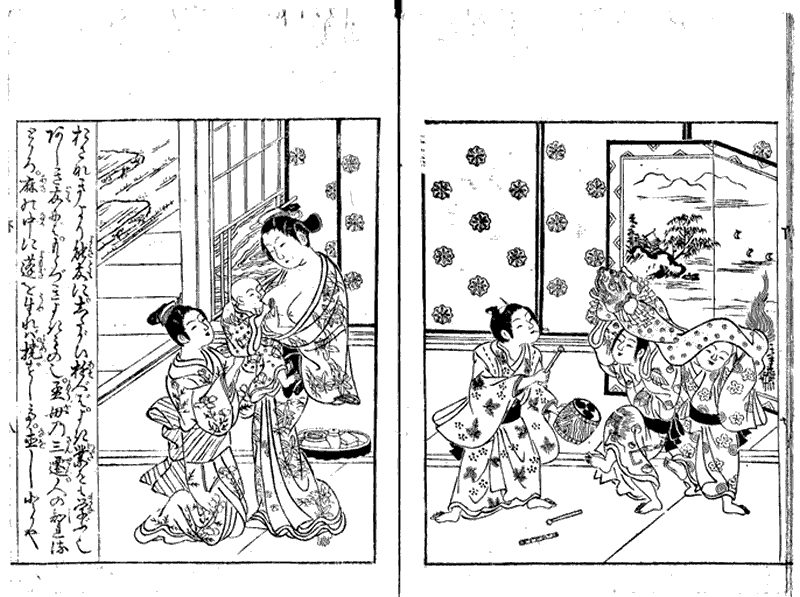 |
(8) (子育ては環境、善き友が大切) おさなきより あしき友には。もとづきにるもの也。孟母の三遷。人の知れる ところ。麻の中に |
| ○孟母三遷 諺。〈故事〉環境が子どもに与える 影響を考えて、孟子の母が三度住居を移して孟子 の教育につとめた故事。墓地近くに住むと埋葬の まねをし、市中に移ると、商売のまねをしたので、 学校の近くへと移転した。〔列女伝〕 |
○麻の中の蓬(よもぎ) 諺。[荀子勧学「蓬生麻中不扶而直」] まっすぐに伸びる麻の中に生えれば、曲がりやすい ヨモギも自然にまっすぐ伸びる。人も善人と交われば、 その感化を受けて善人となる。 |
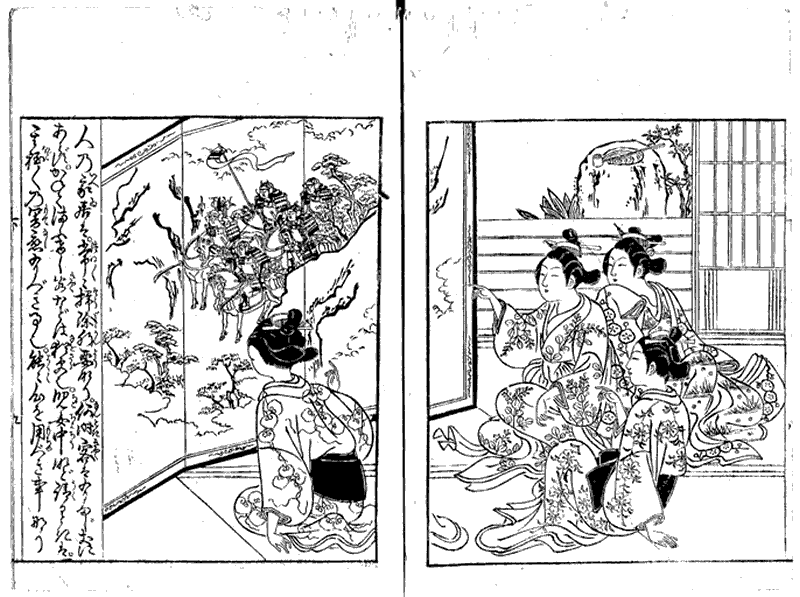 |
(9) (掃除、客、女中への気遣い) 人の家居は常々掃除肝要なり。何時客は有まじきに あらず。かねて、 其 |
|
、 |
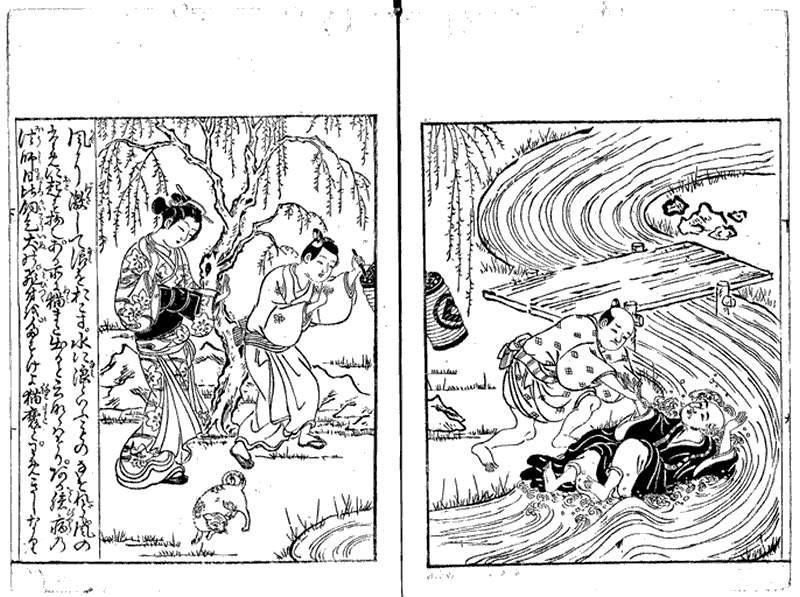 |
(10) (猫又) 風に激して浪をおこす。水に浪といふことのなけれども風の ために起す物也。ある所に猫また出ると云ならハせり。ある 法師。日頃 |
|
*飼乞 (かいこう) 飼養(かいかう)ふ |
*猫股・猫又 猫が年老いて尾が二つにわかれ、よく化けると いわれるもの。 徒然草「奥山に猫又といふものありて」 絵本徒然草 (第八九段)猫股参照 (絵双紙屋HP) |
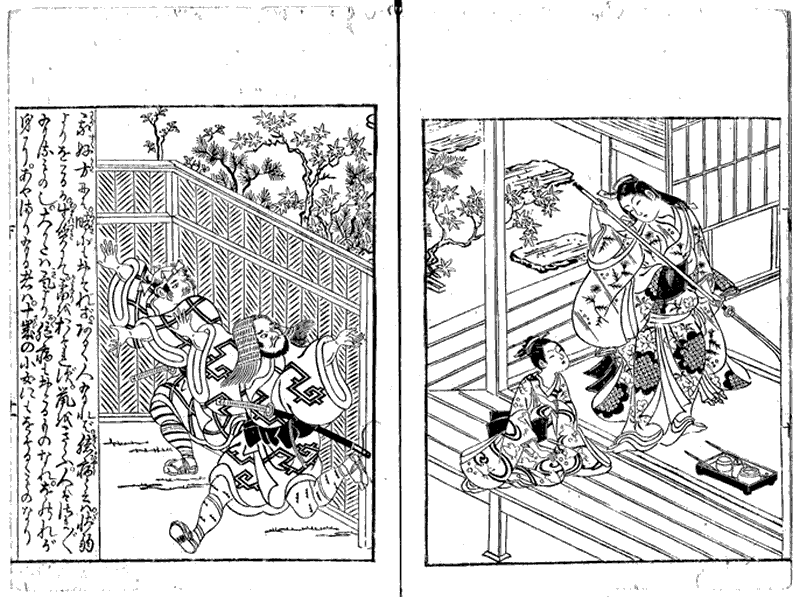 |
(11) (憶病は気よりおこる) よりをこるか。 有るもの也。大かたハ。気より臆病もおこるものなれ。をのれが 身に。あやまり有る者ハ。十歳の少女にもをそるゝものなり |
|
*事由(じ‐ゆう)ことの理由・原因。 |
○臆病者は義理知らず 臆病者は何か困難なことがある とすぐ逃げだし、なすべきことを果たさないため、結 果的に義理を欠く。 |
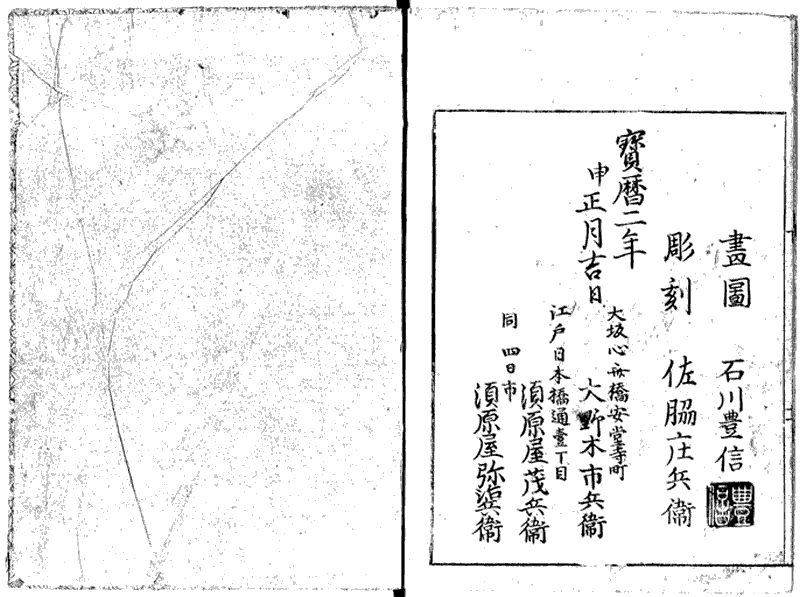 |
(12) 画図 石川豊信 彫刻 佐脇圧兵衛 宝暦二年 申正月吉日 大坂心斎橋安堂寺町 大野木市兵衛 江戸日本橋壹丁目 須原屋茂兵衛 同 四日市 須原屋弥治兵衛 |